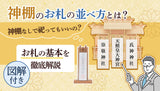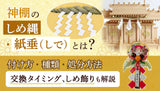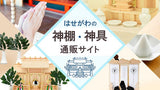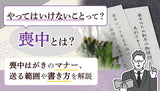お仏壇を置く意味と配置・飾りの考え方

お仏壇は、ご本尊やご先祖様を祀り、日々手を合わせて感謝や祈りを捧げるための大切な場所です。家庭に置くことのできる小さなお寺ともいわれ、仏様の世界やお浄土を表しています。
かつては仏間や床の間に置くことが一般的でしたが、現代ではリビングなど、ご家族が集まりやすい場所に設置されることも増えています。お仏壇の配置や飾り方には、宗派に応じた基本の考え方がありますが、住宅事情に合わせて柔軟に対応されるとよいでしょう。
>>お仏壇への仏具の飾り方を確認
>>お仏壇の置き場所・方角を確認
お仏壇の飾り方(浄土真宗以外の宗派)

お仏壇の飾り方や必要な仏具は、宗派により異なります。
また、お仏壇のサイズやデザインによっては、正式な飾り方を省略する場合もありますので、お仏壇を置くスペースだけでなく、お仏壇内部の寸法も事前に確認をしましょう。
ここでは宗派ごとの違いと一般的な飾り方について詳しく解説します。
一般的な飾り方
浄土真宗以外の宗派で一般的な飾り方をご紹介します。宗派やお寺、地域により異なることもありますので、購入前にはお寺に確認すると安心です。
コンパクトなサイズのお仏壇ではお仏具を全てお飾りすることが難しい場合もあります。そのような中でも下記のお仏具は最低限用意されるとよいでしょう。
■仏具の種類について詳しくはこちら
仏具の種類を画像付きで徹底解説いたします。また、近年人気が高まっているモダンな仏具もあわせてご紹介しています。
台の上に置くタイプ
台の上に置くタイプのお仏壇は内部の空間が狭くなりますのでお飾りも簡略化の傾向があります。「仏様の世界」を表すものですので、なるべくお仏具をしっかり揃え、床から置くタイプのように正式な飾りが望ましくはあります。
この飾り方は普段のお飾りともいえますので、床から置くタイプのお仏壇も普段や内部の空間スペースがとれない場合はこちらを参考になさってください。


おすすめ上置き仏壇
床から置くタイプ
床から置くタイプのお仏壇は内部の空間が広くなっており、お飾りをゆったりと置くことができます。
四十九日や回忌法要、お盆、お彼岸など特別な行事の際には、正式なお飾りをしましょう。正式にはお花立と火立を対にします。幢幡(どうばん)、大小2枚の打敷(うちしき)を飾り、御霊具膳(おりょうぐぜん)に精進料理をもります。
※日蓮宗では木魚ではなく木征を用います。


近年ではお仏壇のモダン化やコンパクト化もあり、お飾りするスペースを十分に確保できないこともあります。その場合は、【台の上に置くタイプ】の飾りを参考にするとよろしいでしょう。
はせがわ店舗では専門スタッフが実際にお仏壇に仏具を飾りながら、宗派に合ったご提案をさせていただきます。
はせがわの店舗はこちら>>
おすすめ床置き仏壇
宗派ごとのご本尊・脇侍
お仏壇のお飾りで特に重要なのがご本尊と脇侍です。各宗派の象徴・お参りの対象として、お仏壇の最上段へお祀りします。 お参りの際、ご本尊をやや見上げる高さなるようにご安置しましょう。
| 宗派 | 脇侍(左) | 本尊(中央) | 脇侍(右) |
|---|---|---|---|
| 天台宗 | 伝教大師 | 座弥陀 | 智者大師 |
| 真言宗 | 不動明王 | 大日如来 | 弘法大師 |
| 浄土宗 | 法然上人 | 阿弥陀如来 | 善導大師 |
| 浄土真宗本願寺派 | 蓮如上人 | 阿弥陀如来 | 親鸞聖人 |
| 真宗大谷派 | 九字名号 | 阿弥陀如来 | 十字名号 |
| 臨済宗 | 普賢菩薩 | 釈迦如来 | 文殊菩薩 |
| 曹洞宗 | 常済大師 | 釈迦如来 | 承陽大師 |
| 日蓮宗 | 鬼子母神 | 御曼荼羅・三宝尊・ 日蓮聖人 |
大黒天 |
※日蓮宗の脇侍はお寺・地域により左右の配置が異なることがあります。
■ご本尊について詳しくはこちら
各家庭のお仏壇に、仏像や掛軸のご本尊をどのようにお祀りすればいいか詳しく解説しています。
浄土真宗の飾り方

浄土真宗本願寺派、真宗大谷派でのお飾りをご紹介します。多くの宗派では位牌をお祀りしますが、浄土真宗では位牌を置かず、過去帳や法名軸を用いるのが基本です。
浄土真宗 本願寺派(お西)
正式なお飾りでは香炉・花立・火立はお仏壇の中央になります。打敷の上に香炉、その両脇に花立・火立を対で並べます。天井からは瓔珞(ようらく)・輪灯(りんとう)をさげます。お餅や落雁をさしあげる供笥(くげ)を対で飾ります。
普段は簡易なお飾りになります。打敷を外し、供笥もお供えがない時はしまいます。仏飯器(ご飯のお供え)はご本尊の前だけで略し、中段の花立・火立も対の必要はありません。普段の飾り方は小型なお仏壇にも適しています。

浄土真宗 真宗大谷派(お東)
正式なお飾りでは香炉・花立・火立はお仏壇の中央になります。打敷の上に香炉、その両脇に花立・火立を対で並べます。天井からは瓔珞(ようらく)・輪灯(りんとう)をさげます。ご本尊の前に仏飯器を2つ並べます。お餅や落雁をさしあげる供笥(くげ)を対で飾ります。
普段は簡易なお飾りになります。打敷を外し、供笥もお供えがない時はしまいます。仏飯器(ご飯のお供え)はご本尊の前だけで略し、中段の花立・火立も対の必要はありません。普段の飾り方は小型なお仏壇にも適しています。
※一対の火立は左右の向きに注意しましょう。(鶴の口ばし右開き、亀の尻尾は手前向き)

※真宗大谷派は東本願寺といういい方をすることもあります。
■浄土真宗の飾り方について詳しくはこちら
浄土真宗の仏具の基本的な飾り方を写真付きで分かりやすく解説します。
自由な飾り方も増えています


最近ではステージタイプのお仏壇などの自由な飾り方も増えています。故人様を想い素敵な祈りの空間をつくられてはいかがでしょうか。
仏具セット付モダン仏壇
どの部屋に置くべき?仏壇の置き場所

お仏壇を置く部屋には決まりはございませんが、「ご家族が毎日手を合わせやすい場所」がおすすめです。
お仏壇の配置に適した部屋・条件
- リビング
- 和室(仏間・床の間)
- 寝室 など
また、次のような環境条件に注意しましょう。
- 直射日光が当たらない場所(色あせや劣化を防ぎます。)
- 湿気が少ない場所(カビや木材の反りを防ぎます。)
- 冷暖房の風が直接当たらない場所(乾燥やひび割れを防ぎます。)
お仏壇の向き・方角に決まりはある?

お仏壇を配置する向きや方角について、明確な決まりはありませんが、いくつか代表的な考え方があります。
- 南面北座説(なんめんほくざせつ):お仏壇を南向きに置き、お参りする人が北を向くパターンです。お釈迦様が説法をする際、南を向いて座ったという言い伝えから、曹洞宗・臨済宗で見られる置き方です。
- 西方浄土説(さいほうじょうどせつ):お仏壇を東向きに置き、お参りする人が西を向くパターンです。極楽浄土が西の方角にあるとされることが由来で、浄土真宗・浄土宗・天台宗で見られる置き方です。
- 本山中心説(ほんざんちゅうしんせつ):お仏壇を各宗派の本山がある向きに置き、お参りする人は本山の方角を向く置き方です。真言宗などで用いられる置き方です。
また、全ての向きにお浄土がある(仏様がいらっしゃる)との考えから、方角は気にせずよいとする「十方浄土説(じっぽうじょうどせつ)」などもあります。
諸説ありますが、ご家族がお参りしやすい場所と方向を選ぶことが最も重要です。
■仏壇の置き場所について詳しくはこちら
お仏壇を置く向きや適した置き場所、避けるべき場所など仏壇配置の基本を解説します。
よくある質問

お仏壇の飾り方や置き方に関するよくある質問について回答します。
Q1. お仏壇の設置後に法要などは必要ですか?
A1. 菩提寺によってはお仏壇に「開眼供養(魂入れ・仏壇開き)」を行う場合があります。
実施の可否、日時や場所について事前に相談されると安心です。
Q2. 日常のお供え物は何が必要でしょうか。また、どのように飾ればよいでしょうか。
A2. 日々のお参りには「五供(ごく)」と呼ばれる考えに基づき、「香・灯明・花・飲食・浄水」の5つを基本としてお供えします。
- 香(こう)…香炉でお線香を焚き、清浄な空間を整えます。
- 灯燭(とうしょく)…火立にローソクを灯し、仏様の智慧の光を表現します。
- 花(はな)…花立に季節の花を供え、命の尊さを表します。(花はお参りする人のほうへ向けます。)
- 飲食(おんじき)…仏飯器にご飯、高杯に果物をお供えします。
- 浄水(じょうすい)…湯呑に水やお茶をお供えします。
お仏壇へのお参りの仕方を動画で解説
お仏壇の基本的なお参りの流れや、知っておくと役立つマナーを解説しております。
参照動画:教えて!! はせがわさん 初めてお仏壇にお参りする方へ ※動画が再生できない場合はこちら >>
■お仏壇のお供え物について詳しくはこちら
仏壇には何をお供えする?正しい供え方・宗派の違い・タブーを解説
お仏壇へのお供え物の定番である「五供(ごく)」を中心に、基本的なお供え物や供え方、タブー(供えてはいけないもの)などを具体的に解説いたします。
Q3. お仏壇の扉は、お参りの度に閉めたほうがよいでしょうか?
A3. 開けたままでかまいません。
いつでもご先祖様に見守っていただけるように、私たちが手を合わせられるようにと考えられています。朝に扉を開けて、夜に閉めるといった習慣もあります。
Q4. お仏壇の中に写真を飾ってはいけないと聞きましたが本当ですか?
A4. タブーではありませんが、手を合わせる対象はご本尊やお位牌であるという考えから、一般的にはお仏壇の内部にお写真は飾りません。
しかしながら、写真で故人様の顔を見たいという気持ちも強いものです。遺影の場合は和室の鴨居に飾ることが多く、小さいお写真であれば、お仏壇の手前や横に台を用意して置かれるのもよいでしょう。
Q5. お仏壇や仏具の掃除をしたいのですが、飾り方がわからなくなりそうで不安です。また、気をつけるポイントがあれば教えてください。
A5. 事前に仏具をお飾りした状態の写真を撮っておくことをおすすめします。
陶器製の湯飲みなどは食器同様に洗いますが、絵付けが細かい場合はこすらないようにしましょう。それ以外のお仏具は基本的に薬品を使用せずにやわらかい布や毛払い(毛ばたき)を用いるとよいでしょう。
お仏壇のお手入れの仕方を動画で解説
お仏壇の基本的なお手入れ方法や、お位牌・仏具のお掃除方法を解説しています。
教えて!!はせがわさん 初めてお仏壇のお手入れをする方へ ※動画が再生できない場合はこちら >>
お仏壇の掃除用品
■お仏壇掃除について詳しくはこちら
お仏壇の掃除でやってはいけないことはある?掃除方法の基本を解説
お仏壇掃除のやり方や頻度など、お仏壇のお手入れ方法全般を解説いたします。
Q6. お仏壇の置き場所が確保できず悩んでいます。お仏壇の代わりに場所を取らずにできるご供養の方法はありますか?
A6. 近年は、「手元供養」を取り入れるご家庭も増えています。
代表的な手元供養品と飾り方は以下の通りです。
- ミニ仏壇・飾り台(ステージ):一般的なお仏壇より場所を取らず、香炉やリンと合わせて祈りの場を作ることが可能です。
- ミニ骨壺:小型の骨壺にご遺骨の一部を収蔵し、お仏壇内の一角やリビングの小さな台に置くことができます。
- 遺骨ペンダント:ごく少量のご遺骨を収められるアクセサリーです。身につけ、持ち歩くことが可能です。
手元供養関連商品
■手元供養について詳しくはこちら
手元供養の意味、メリットとデメリット、手元供養品の種類とやり方を解説します。