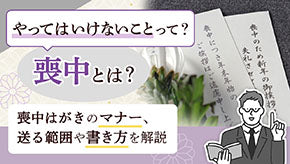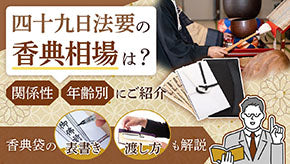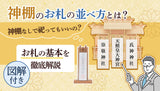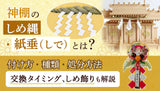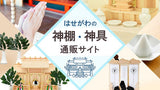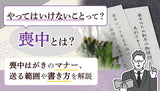「法要」と「法事」の違いとは?

法事や法要といえば、四十九日や初盆、一周忌や三回忌といったものが思いつくのではないでしょうか?法事には様々な種類があり、亡くなってから何日・何年目になるかによって、執り行う法要の名称や内容が変わります。
以下では、混同しやすい法事と法要について解説します。
「法要」と「法事」の意味
「法要」は故人様の冥福を祈り、住職による読経や参列者の焼香など、ご供養をするために行う仏教の儀式のことを指します。
一方で「法事」は、住職に読経していただき故人様を供養する「法要」と、その後の会食などを含めた仏教行事全般を指します。法要は主に「忌日法要」と「年忌法要(年回法要)」の2種類があります。
忌日(きにち・きじつ)法要
忌日法要は、故人様が亡くなってから7日経つごとに行われる追善供養※を行うことです。
仏教では、人が亡くなると49日間はこの世とあの世をさまようと考えられています。この期間を「中陰(ちゅういん)」と呼び、亡くなった方の霊をあの世へ旅立たせるために7回の忌日法要を行います。
遺族は七七日(亡くなってから49日目に行われる法要)までの間、喪に服し行動を慎む「忌中」となります。
※追善供養…亡くなった方が無事成仏してよき来世に生まれ変わるよう、この世に生きている人が故人の代わりとなって善行(法要)を行うことです。
■忌中や喪中について詳しくはこちら
喪中と忌中の意味や期間中の注意点を解説しているページです。あわせて、喪中はがきを出すタイミングや送る範囲、書き方などについても解説しています。
年忌法要(年回法要)
年忌法要とは、故人様の命日のうち決められた年に行う13回の追善供養を行うことです。
一周忌のあと、2年目の命日に行う「三回忌」以後、七回忌(6年目)、十三回忌(12年目)、17回忌(16年目)と訪れる三と七がつく年に、参列者を招いて追善供養します。地域や宗派によっては、年忌法要を行う年が異なる場合があります。
正式には五十回忌をもって弔い上げとされますが、一般的には三十三回忌が終わると故人様は完全に成仏すると考えられています。また、最後の法要は「年忌明け」とも呼ばれます。
年忌法要を行うタイミングは「故人様が亡くなってから経った年数」へ「1」を足した数字に3と7が含まれている年の祥月命日、と覚えましょう。
法要の種類について解説

法要には様々な種類があります。全ての法要を行うことが難しい場合、遺族の負担や参列者のご都合などを考慮して、特に重視される法要(四十九日、百カ日、一周忌、三回忌)以外は省略したり、祥月命日が近い他のご先祖様と一緒に法要を執り行う「併修(へいしゅう)」をしても問題ないとされます。
家族や親族、菩提寺やお付き合いのある寺院によっても法事や法要に対する考え方が異なる場合があるため、追善供養をどう行っていくかについて事前に確認しておきましょう。以下では、法要の種類について解説します。
1年目に行う法要の種類
| 初七日(しょなのか・しょなぬか) | 命日から7日目に行う忌日法要 |
| 二七日(ふたなのか) | 命日から14日目に行う忌日法要 |
| 三七日(みなのか) | 命日から21日目に行う忌日法要 |
| 四七日(よなのか) | 命日から28日目に行う忌日法要 |
| 五七日(いつなのか) | 命日から35日目に行う忌日法要 |
| 六七日(むなのか) | 命日から42日目に行う忌日法要 |
| 七七日(なななのか・四十九日) | 命日から49日目に行う忌日法要 |
| 百カ日(ひゃっかにち) | 命日から100日目に行う法要 |
| 新盆(初盆)法要 | 忌明けに初めて迎えるお盆に行う法要 |
初七日(しょなのか・しょなぬか)
故人様が亡くなってから7日目に行われる忌日法要です。
初七日は、故人様が三途の川に到着する頃です。秦広王(しんこうおう・不動明王)によって、故人様は生前に犯した殺傷の罪について審判され、その結果によって三途の川が渡れるかが決まります。無事に川を渡れるように祈り、参列した遺族や親族、故人様と縁のあった方々が住職による読経とあわせてお焼香をします。
法要は自宅か寺院のどちらの場所で行うか、住職や親族のお考えも考慮しながら決定します。また昨今では、葬儀と同日に初七日法要を合わせて執り行う「繰り上げ法要(繰り込み法要)」も増えています。
二七日(ふたなのか)
故人様が亡くなってから14日目に行われる忌日法要です。
ニ七日は初江王(しょこうおう・釈迦如来)によって、故人様が生前に犯した盗みの罪について審判されます。
三七日(みなのか)
故人様が亡くなってから21日目に行われる忌日法要です。
三七日は宋帝王(そうていおう・文殊菩薩)によって、故人様が生前に犯した不貞の罪について審判されます。
四七日(よなのか)
故人様が亡くなってから28日目に行われる忌日法要です。
四七日は五官王(ごかんおう・普賢菩薩)によって、故人様が生前についた嘘の罪について審判されます。
五七日(いつなのか)
故人様が亡くなってから35日目に行われる忌日法要です。
近親者と僧侶のみで読経を行い故人の冥福を祈るのは、これまでの法要と同様です。しかし、地域によっては五七日法要を忌明け日として、忌明け法要を執り行うところもあります。
五七日は閻魔王(えんまおう・地蔵菩薩)によって、故人様が生前に犯したすべての罪が審判され、六道※のうちどの世界に生まれ変わるかが決定します。
※六道…全ての生き物が輪廻転生(死んでは生まれ変わること)する、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天(神々)の6つの世界のことです。
六七日(むなのか)
故人様が亡くなってから42日目に行われる忌日法要です。
六七日は変成王(へんじょうおう・弥勒菩薩)によって、五七日で決定した生まれ変わる先の世界にて、故人様が生まれる場所やどのような立場となるかが詳しく決められます。
七七日(なななのか・四十九日)
故人様が亡くなってから49日目に行われる忌日法要です。
一般的には四十九日と呼ばれ、法要の中でも特に重要な行事とされています。
七七日は泰山王(たいざんおう・薬師如来)によって、故人様が来世での性別や寿命などが決められ、最後の判決が下されます。
お位牌やお墓に魂を入れることは「開眼法要(お性根入れ)」と呼ばれ、自宅で祀られていた白木位牌は多くの場合、この法要をもって本位牌へ魂が移され、お墓があれば同時に納骨も行います。この日から遺族は「忌明け」となり、喪に服していた生活から元の生活へ戻ります。
■四十九日法要について詳しくはこちら
四十九日法要の意味や準備方法のほか、家族のみで法要を執り行う場合について解説しているページです。また、お布施や香典の相場や服装、挨拶の仕方などマナーについても紹介しています。
百カ日(ひゃっかにち)
故人様が亡くなってから100日目に行われる法要です。
「卒哭忌(そっこくき)」とも呼ばれ、遺族が故人を亡くした悲しみから解放される日とされています。忌明けに行うことが一般的な「納骨法要」については、百カ日の法要や一周忌に執り行う場合があります。
新盆(初盆)法要
新盆(にいぼん)…故人様の四十九日後の忌明けに初めて迎えるお盆のことです。四十九日前にお盆が訪れる場合は翌年に新盆を行います。
新盆法要とは、故人様が亡くなってから初めて迎えるお盆に行う法要です。
新盆は、親族や知人友人など大勢で丁寧にお迎えするべき行事とされており、お寺や自宅で新盆法要を行うことが一般的です。
お盆では毎年、お供え物や提灯で仏前を華やかにして故人様の霊をお迎えします。また新盆は一部宗派を除き、故人様へ我が家を知らせる目印として白紋天(しろもんてん・白い提灯)を玄関の前や軒先にお飾りします。
■新盆法要について詳しくはこちら
新盆法要の準備方法をはじめ、お布施の金額相場・表書きの書き方、法要当日の服装マナーなど、新盆法要を行う際に必要な基礎知識を解説しているページです。
2年目以降で重視される法要
決められた年の祥月命日には年忌法要を執り行い、追善供養をすることが正式な形とされます。昨今では、数ある法要の中でも特に重視されている「一周忌」「三回忌」「三十三回忌」といった年忌法要のみ行い、そのほかの法要を省略するという場合もありますが、家族や親戚、住職のお考えも考慮して実施するかを決定しましょう。
以下では、基本的に行われている年忌法要について解説します。
一周忌
故人様が亡くなってから1年目の祥月命日に行われる法要です。
亡くなった翌年の祥月命日は、数ある法要の中でも大切にされています。四十九日の法要と同様に住職のほか、故人の親族や生前に縁があった人など多くの方が参列し、盛大に行います。
■一周忌と一回忌の違いとは?
一回忌は「一番最初の祥月命日」という意味で、故人様が亡くなった当日のことを指します。一方で、一周忌は「一回忌から2回目の祥月命日」です。一周忌と一回忌は意味を間違えやすいため注意しましょう。
三回忌
故人様が亡くなってから2年目の祥月命日に行う法要で、数ある法要の中でも重要な意味を持つとされています。また一般的には、一周忌と同様に多くの参列者を集める法要とされていますが、近親者のみで慎ましやかに執り行うという場合もあります。
亡くなってから2年目が三回忌となり、二回忌と呼ばないため注意しましょう。
三十三回忌
故人様が亡くなってから32年目の祥月命日に行う法要です。
三十三回忌では法要による供養の区切りとして、故人様が完全に成仏したと考え弔い上げを行い、以降の年忌法要は実施しなくなるのが一般的です。弔い上げの考え方は、宗派の教えや地域によって異なりますので、菩提寺や地域に詳しい方へ確認しておくと安心です。
■三十三回忌以降の回忌法要
三十三回忌以降の法要も他の年忌法要と同様に、住職の読経による追善供養を執り行うのが正式な形ですが、それまでの法要よりも規模は小さくなる傾向があり、基本的には住職と親族のみで執り行われる場合が多いです。また、三回忌や三十三回忌などを最後の法要として、三十三回忌以降は行わない方針のご家庭もあります。
住職や家族と相談し、法要を何回忌まで行うかを確認して計画的に執り行いましょう。
そのほかの法要
彼岸法要
お彼岸とは「春分の日・秋分の日を中日とした7日間」のことで、現代ではご先祖様へ感謝の気持ちを込めて供養を行い、自身も仏教の教えに従って精進すべき期間として知られています。
お彼岸には、ご自宅のお仏壇へのお供えやお墓参りのほか、法要を執り行うことがあります。
■彼岸法要について詳しくはこちら
お彼岸法要における、お布施相場・服装などの基礎知識とマナーを解説しているページです。また、お墓参りで立てる「塔婆(とうば)」についてもご紹介しています。
施餓鬼会(せがきえ)
施餓鬼会(施餓鬼法要)とは、死後に六道の一つである「餓鬼道(がきどう)」に落ちて餓鬼になった人や無縁仏など、飢えに苦しんでいる死者の霊魂に食べ物や飲み物などを施して供養する法会(儀式)のことです。曹洞宗では施食会(せじきえ)とも呼ばれています。
行う時期に決まりはない法要ですが、お盆(7月・8月)、春彼岸(3月)、秋彼岸(9月)のタイミングで、寺院にてご先祖様の追善供養のために実施することが多いです。全国にある多くの寺院では、お盆の時期に盆法要と合わせて施餓鬼法要を開催しています。
■施餓鬼会について詳しくはこちら
施餓鬼の意味、目的やお布施の相場について解説しているページです。また、お盆との関係や宗派による違い、法要の流れとマナーにも触れて解説しています。
法事まではどうする?準備の流れ

四十九日法要の準備は1か月前、一周忌法要は2~3か月前から行うのが一般的とされ、いずれの場合も可能な限り早めの準備がおすすめです。家族や親族で協力しながら進めていくとよいでしょう。以下では、法事の前に必要な準備について解説します。
施主や遺族が準備する流れ
①日時を決めて会場を手配する
まずは住職や親族と相談し、法要を行う日時を決めます。
祥月命日が平日の場合、参列者の都合を配慮して集まりやすいよう、直前の土日にずらして執り行われることが多いです。法事の会場にできる場所は、自宅や寺院のほか、法要会場やホテルなどもあります。
■法事をやってはいけない日とは?
法事をやってはいけない日はないとされていますが、友引や赤口、国民の祝日は避けるべきと考えられる場合もあります。そのほか、親族の結婚式などのお祝い事が先に予定されていた場合は、同日を避けたほうがよいとされています。
②住職への依頼とお布施の準備
菩提寺やお付き合いのある寺院の住職へ連絡をして、法要に来ていただくための依頼をします。
お盆やお彼岸などは住職の都合が合わない場合もありますので、早めに日時を確認しておきましょう。
また、お渡しするお布施(法要のお礼として渡す金銭)を準備しておきます。法事でお渡しするお布施の相場は、3万円~5万円程ですが、法要の内容や地域、寺院によって金額が変化することがあります。相場について迷われる場合は、住職に直接確認いただいても問題ありません。
③参列者へ案内状を送る
法要を執り行う手配が進んだ後は、参列していただきたい親族や故人様と縁のあった方を選び、案内状を送ります。
返信をみてから最終的な参列者数を確定しましょう。案内状には返信用はがきを同封しておくと丁寧です。また返信の期限を記載しておくと、スムーズに次の手配が進められます。
④会食の予約と引き出物を用意する
参列者数が決まった後は、会食の予約を行い、引き出物(返礼品)を用意します。
会食場所は、寺院や霊園、葬儀場、自宅、ホテルなど様々あり、会場に合わせて仕出し弁当の用意や食事の予約を行います。また寺院や霊園の施設を利用する場合、指定の業者があるか確認しておきます。
会食をする場合、住職が辞退された際には「御膳料」をお渡しするため、事前に確認しておきます。法要後の会食は地域によって実施されないことがあるため、気になる場合は住職や葬儀の担当者へ確認されるとよいでしょう。
引き出物とは、香典やお供え物を持って法要に参列いただいた方々に対して、法要当日にお礼としてお渡しする品物のことです。引き出物は、5,000円~1万円程が一般的な相場とされていますが、参列者とのお付き合いの深さによっても異なります。
参列者の服装やお供え物はどうする?

法事では、どのようなことに気を付けなければならないでしょうか?以下では、法事に参列する際の服装マナー、香典やお供え物について解説します。
参列者の服装
喪主や親族は正喪服もしくは準喪服を着用し、参列者は準喪服を着用するのが正式な形ですが、法要の内容や規模によって異なります。一般的に、忌日法要から一周忌までは参列者全員が喪服を着用します。
案内状に「平服でお越しください」と記載される場合がありますが、法事での「平服」とは普段着という訳ではなく、スーツやワンピースなどフォーマルな服装を指しますので注意しましょう。また、服の色は黒や茶、グレー、紺などの落ち着いた色を選ぶことがマナーとされています。
■法事の服装について詳しくはこちら
3つの喪服の種類、法事ごとに着用する喪服について男性・女性・子ども別に解説。
お渡しする香典やお供え物
香典
法事に参列する際は、香典(故人様の霊前にお供えする金銭)をご供養に使っていただくために遺族へお渡しします。香典は不祝儀袋に包み、袱紗(ふくさ)に包んで会場の受付などで渡します。不祝儀袋の表書きは、四十九日までに渡す場合「御霊前」、四十九日を過ぎてからであれば「御仏前」と記載します。
不祝儀袋・袱紗(ふくさ)
■四十九日法要の香典について詳しくはこちら
四十九日法要の香典について、相場を各方面から解説しているページです。 また、香典袋の表書きや当日の渡し方などの基本マナーも紹介しています。
お供え物
法事で贈るお供え物は、食べ物や線香などの「消えもの」を選ばれることが多く、相場は法事の内容に寄って異なりますが5,000円~1万円程が一般的です。お供え物は、故人様や遺族の方へ気持ちを込めて贈りましょう。
贈答用線香・法事ギフト
よくある質問

最後に「法事」「法要」に関してよくお寄せいただく質問をご紹介します。
Q1.法事の当日に用意するものはなに?
A.故人様のお位牌、お寺様へのお礼であるお布施、お供え物(果物やお菓子)、供花などが挙げられます。
法事で用意すべきものは、法要の種類や執り行う場所、当日のスケジュールによっても変わってまいります。法事に必要なものについて、葬儀社のご担当者様や住職に確認されることをおすすめします。
Q2.法要の受付を担当する際、用意するものや気を付けることは?
A.参列者様を把握するための芳名帳と筆ペン、香典を受け取るためのお盆が必須となります。
その他の詳細については、葬儀社のご担当者様などに確認しておくと漏れなくご準備いただけます。
Q3.法要は「仏滅」「先負」などの日を選ばないとだめ?
A.仏教の教えには六曜の考え方は入っていないため、特に気にされる必要はございません。
年忌法要を行う日で最も良いのは祥月命日ですが、多くの場合には、参加者の都合を考えて、直前の土日祝日の日程を選ぶのが一般的です。
法事や法要に関する内容をはじめ、はせがわではご供養全般のご相談を承っております。ぜひお気軽にお近くの店舗までお越しください。
>>お近くのはせがわ店舗を探す