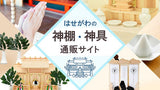花祭りとは?いつ行われるの?

花祭りはお寺のほか、仏教系の学校や幼稚園などでも催されることが多く、子供から大人まで広く親しまれている仏教行事です。以下では、花祭りの意味や歴史、名前の由来について解説します。
花祭りはお釈迦様の誕生を祝う行事
花祭りとは、お釈迦様の誕生をお祝いして、「子どもの身体健全・所願成就」を祈る仏教行事です。
日本各地の寺院ではお釈迦様の誕生日として伝えられる4月8日に「誕生仏(釈迦像)」を囲った小さなお堂の「花御堂(はなみどう)」が安置され、参拝者は誕生仏に甘茶をかけてお祝いします。花祭りは宗派に限定されず、浄土真宗系の寺院などでも開催されており、仏教では重要なお祭りとされています。
また一部地域では、花祭りを旧暦や翌月の5月8日に行う寺院もあります。
■お釈迦様の誕生日は4月8日?
お釈迦様が実際にお生まれになった日は現代でも明らかになっておらず、古くから人々の間で伝えられてきたのが4月8日とされています。
お釈迦様の誕生日は諸説あり、日本や中国などの大乗仏教(利他を行い多くの人を救うための教え)が伝えられた国では4月8日、スリランカやタイなどの上座部仏教(修行を行い悟りを得るための教え)が伝わった国では2月15日(中国や日本での「涅槃の日」)がお釈迦様の誕生日であると考えられています。
花祭りの歴史
花祭りは、お釈迦様が誕生したインドを起源として、中国で盛んに行われるようになった後、日本へ伝わってきました。日本では奈良時代から各地で花祭りが広まっていき、宮中の行事から寺院の年中行事へ変化したと伝えられています。
また、日本で最初の花祭りは、西暦606年に奈良県の元興寺(がんごうじ)で行なわれたお祭りとされています。
「花祭り」の呼び方
花祭り(花まつり)の正式名称は「灌仏会(かんぶつえ)」といい、「甘茶を仏様へ灌ぐ(そそぐ)」ことが由来とされています。
また、花祭りは地域や寺院によって、「竜華絵(りゅうげえ)」「仏生会(ぶっしょくえ)」「花会式(はなえしき)」「降誕会(ごうたんえ)」「浴仏絵(よくぶつえ)」など、さまざまな呼び名で呼ばれています。
灌仏会(かんぶつえ)が「花祭り」と呼ばれるようになったのは、明治時代末頃からとされています。これには、お釈迦様の誕生日が春の花が咲く時期と重なるからという説や、お釈迦様の生まれたルンビニーの花園では美しい花々が咲いていたからという説などがあります。
2025年の花祭りはいつ?
2025年の花祭りは4月8日(火)です。旧暦で開催される地域では5月8日(木)となる場合もあります。
ただし、地域や寺院ごとに開催日が異なることもあるため、詳細はお近くの寺院の情報を事前にご確認ください。
花祭りは何をする行事?どこで行われるの?

「お寺で花祭りが行われているのを見たことはあるけれど、実際にどんなことをするの?」と気になる方もいらっしゃるかもしれません。
この項目では、花祭りで行われる主な儀式や催し、開催場所について簡単にご紹介します。
花祭りで主に行われること
花御堂(はなみどう)に誕生仏を安置する

花祭りでは、たくさんの花でお飾りした花御堂を用意し、花御堂の中心へ皿を敷いた上に誕生仏の像を安置します。
お釈迦様が誕生された時、その場で七歩あるいた後、右手を空へ左手を地へ指さして「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」と言ったとされています。この瞬間のお釈迦様の姿を表した像が誕生仏です。
天上天下唯我独尊とは、「天上でも地上でも、それぞれの私がいちばん尊い」という意味をもちますが、かけがえのない各々の尊厳を示す言葉であるとも考えられています。
誕生仏に甘茶をそそぐ

花祭りでは、花御堂の誕生仏に、参拝者がひしゃくを使って甘茶をそそぐという習わしがあります。これは、お釈迦様が誕生した時に、九つの頭を持つ龍が天から降りてきて、甘露の雨を注いだという言い伝えに由来しています。
甘茶について詳しくは<こちら>の項目をご覧ください。
稚児行列(ちごぎょうれつ)

稚児行列は、子どもたちを仏様に仕える身として行列になって街を歩かせ、子どもたちの無病息災と成長を願う行事です。
花祭りはお釈迦様の誕生を祝うと同時に、子どもたちの健康を祈る行事でもあり、寺院のほか、仏教系の保育園や幼稚園でも稚児行列が行われることがあります。また寺院によっては、仏様へ仕える子として子どもたちに化粧を施し、平安装束を模した衣装を着せて稚児行列を行うところもあります。
白象の模型を引いて巡行する

一部の寺院などでは、白象の模型を子どもたちで引きながら歩いてまわる巡行を行っていることがあります。
お釈迦様の母親である麻耶王妃は、体の中に白い象が入ってくる夢を見てお釈迦様を身ごもったと伝えられています。この言い伝えにより、白い象は神聖な動物として花祭りで親しまれています。
花祭りはどこで行われるの?
花祭りは、浄土真宗や真言宗をはじめ、宗派を問わず全国の寺院で開催されます。築地本願寺や浅草寺、増上寺などが有名な開催地として知られ、参拝者に甘茶をふるまう「甘茶接待」を行う寺院もあります。
また、仏教系の学校でも子どもたちが参加できるお祭り・イベントとして催されています。
そのほか、はせがわの実店舗でも、例年4月上旬に花御堂と甘茶を設置し、花祭りを開催しています。
ご来店の際は、甘茶をかけてお釈迦様の誕生日をお祝いしてみてはいかがでしょうか。
定番の「甘茶」について

花祭りの行事にかかせない甘茶は、寺院で誕生仏にそそいだり参拝後にふるまわれるほか、ご自宅でも楽しむことができます。この項目では、甘茶とは何か、甘茶の作り方について解説します。
甘茶とは?
甘茶は、ユキノシタ科の「アマチャ」という木の葉を蒸して揉んだあと、乾燥させて煎じたお茶のことです。砂糖を入れなくても自然な甘みがあり、漢方薬としても使用されています。
甘茶には甘味効果以外に、厄除けや鎮静作用、抗アレルギー作用など様々な効能があるとされており、カフェインやタンニンを含まないため小さな子供や妊婦の方でも飲むことができます。
また古くより、甘茶を飲むと無病息災で過ごせる、甘茶で赤ちゃんの頭を撫でると元気に育つ、という言い伝えがあります。
甘茶は寺院で配布されている場合、行事を楽しんだ参拝後にふるまわれることがあります。また、寺院へお参りできない場合や気軽に飲みたい場合は、ネット通販で購入しご自宅で楽しむのもおすすめです。
甘茶の作り方
甘茶を淹れる際、1Lの水に対して2~3gのアマチャの茶葉が適切とされる量です。茶葉を多く入れて飲むと、嘔吐などの中毒症状が引き起こされるため、薄味で作ることを心がけましょう。
少量で作る場合
少量の試飲や、1~2人で楽しむ場合は急須で作るのがおすすめです。
沸騰したお湯を少し冷まし、1gの茶葉を入れた急須にお湯を400mlそそいで蓋をした後、5分ほど蒸らしたら完成です。
一度に多く作る場合
大人数に甘茶をふるまう場合は、やかん(もしくは鍋)で作るのがおすすめです。
1Lの水あたり2~3gの茶葉を用意し、お茶パックの袋に入れます。沸騰したお湯にお茶パックを入れて4~5分煮出し、お茶パックを取り出したら完成です。
花祭りでふるまわれる料理・食べ物とは

以下では、花祭りの会食やお供え物として定番のメニューや食材について解説します。
精進料理
花祭りでは、春が旬の食材を用いた精進料理がふるまわれることがあります。
精進料理とは、仏教の教えに則った食材で作る伝統的な料理です。仏教の教えである「五戒」の1つ「不殺生戒」に則り、動物性の食材を避け、旬の野菜や穀物を中心として調理します。精進料理は花祭りやお盆など、仏教の特別な行事でふるまわれています。
■精進料理について詳しくはこちら
お盆の定番料理とは?精進料理などのお供え物、タブーな食べ物を紹介
お盆料理について解説しているページです。お盆のお供え物を中心に、精進料理とは何かについても解説しています。
お仏壇へのお供えにおすすめのフリーズドライタイプ

近年は、水を加えて電子レンジで温めるだけで手軽に作れる、フリーズドライタイプの精進料理セットも人気です。汁物・漬物・煮物・和え物が入っており、ご飯以外はこれ一つでまかなえるため、レシピが不要です。
また、お供えの際使用する「御霊供膳」は5つの器と箸がセットになっており、お仏壇や葬儀後の後飾り祭壇、盆棚などに飾って使用します。
御霊供膳の並べ方についてはこちら>>
御霊供膳・精進料理素材セット
その他 花祭りで定番の食べ物
花祭りでは精進料理の他、風習に倣った食べ物がふるまわれることもあります。
たけのこ
春が旬の食材として有名なたけのこは花祭りでも定番の食材で、精進料理にもよく用いられています。たけのこは土の中から空に向けて伸びて成長する姿が誕生仏に似ているとして、「仏影蔬(ぶつえいそ)」とも呼ばれています。
そら豆
そら豆はたけのこと同様、花祭りでよく食べられている食材です。そら豆は、さやの先が天に向かって伸びることから「仏豆」という別名をもち、仏教では身近な食べ物として精進料理にも用いられています。
うど
春に旬を迎える山菜のうどは、調理次第でほとんどの部分を捨てずに食べられる食材として知られています。うどは漢字で「独活」と書き、お釈迦様が誕生した時におっしゃった「天上天下唯我独尊」に通ずる言葉であるとされ、花祭りの精進料理にも用いられる食材です。
よもぎ餅・草餅
よもぎ餅は、花祭りでは定番とされる食べ物のひとつです。古くから日本では、花祭りの日によもぎ餅や草餅を作って仏様へお供えするという風習があったことから、現代でもよくふるまわれています。
花祭りのお供えには何を選ぶ?おすすめの花やお飾り

花祭りには、決められたお供え物やお仏壇飾りはありませんが、お釈迦様の誕生を祝し、季節の花などでいつもよりお仏壇を華やかに飾られるとよいでしょう。
この項目では、ギフトにもおすすめの花祭りのお供え物をご紹介します。
季節の花
花祭りにお供えする花の種類に絶対的な決まりはありませんが、仏花の定番である菊やユリをはじめ、春の花を取り入れるのもおすすめです。
特に桜、菜の花、カーネーション、キンセンカ、フリージアなどは、華やかで花祭りらしいお供えになります
毒性の花やトゲがある花など、中にはお供えに適さない種類の花もあるため、事前に確認しておくと安心です。
■仏花について詳しくはこちら
お仏壇やお墓に供える「仏花(ぶっか)」について、基本的な選び方やタブー、飾り方などの基礎知識を解説します。また、造花・プリザーブドフラワーのお供えもご紹介しています。
はせがわ仏花の定期便
【ご多忙な方にもおすすめ!仏花の定期便】
はせがわでは、お忙しい方やお花選びでお困りの方におすすめの「はせがわ 仏花の定期便」を提供しております。
お花のプロがコーディネートした新鮮な生花を定期的にお届けします。(週1回、隔週、月1回コースからお選びいただけます。)
桜の香りの線香

花祭りにお供えするお線香は、桜の香りがおすすめです。
少煙タイプで優しい香りのお線香「香のたより さくら」は、贈答品としても人気が高い商品です。桐箱入りはギフトに、紙箱入りはご自宅用におすすめです。
香のたより さくらシリーズ
春をイメージした和菓子・お菓子

本物の和菓子をお供えすることが難しい場合は、和菓子をモチーフとしたちりめん飾りのお供えがおすすめです。
お香の香り付きちりめんシリーズの「甘美」は内部に良い香りのするお香が包まれており、「香り」をご馳走として召し上がる仏様へのお供え物にぴったりです。手のひらサイズですので、置き場所も選びません。
お仏壇に飾る場合は、お菓子や果物をお供えするための「高杯(たかつき)」という器などの上に乗せて飾るといいでしょう。
お香の香り付きちりめんシリーズ
まとめ

花祭りは全ての宗派に共通する特別な行事です。寺院での催しに参加するほか、ご自宅で甘茶を飲んだり、お仏壇に華やかなお花をお供えしたりすることもおすすめです。ご家庭に合った方法でお釈迦様の誕生日をお祝いしましょう。
はせがわでは、お仏壇や神棚に関する内容をはじめ、ご供養全般のご相談を承っております。ぜひお気軽にお近くの店舗までお越しください。
>>お近くのはせがわ店舗を探す