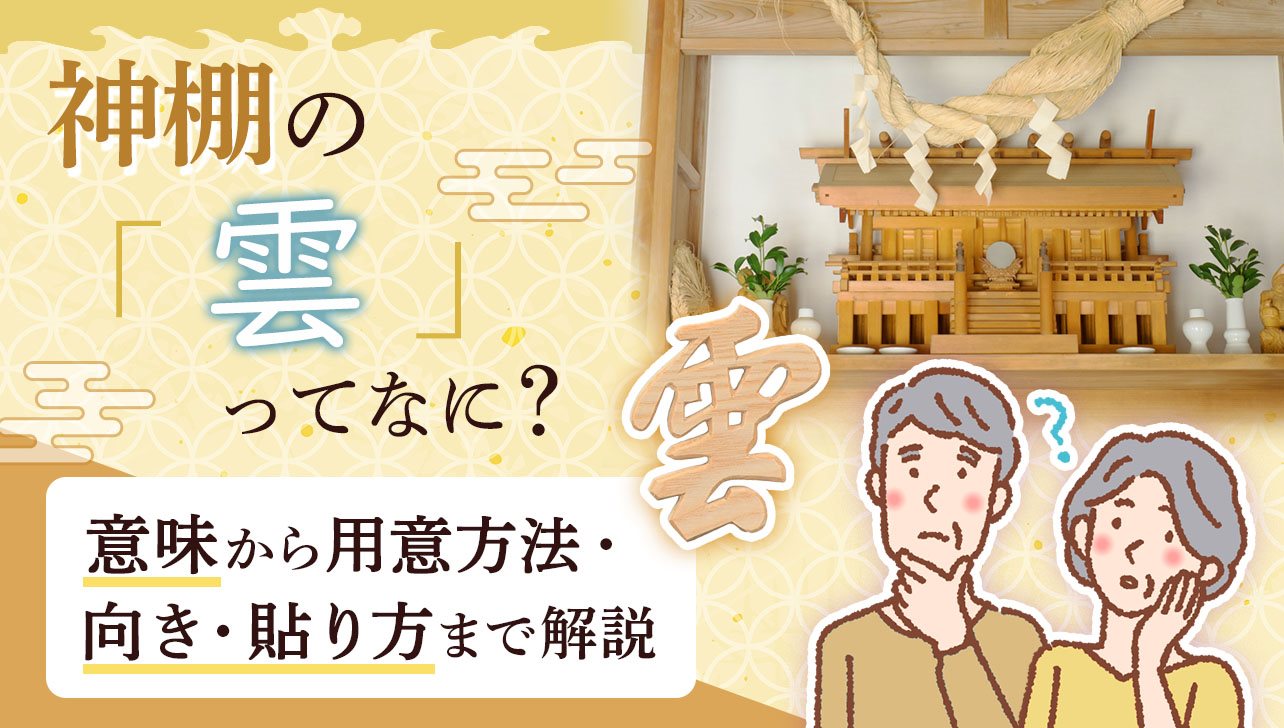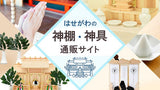神棚とは?どんな意味があるの?

神棚とは、家庭内で神様をお祀りするための場所で、神社で祈祷を受けたお札を祀り、榊などのお供え物を供えるのが基本です。正式には、神様をお祀りする場所を「神棚」、神社の建物を模したものを「宮形(みやがた)」と呼びます。
江戸時代、「お伊勢参り」の流行とともに、伊勢神宮のお札である「神宮大麻(じんぐうたいま)」が全国に広まりました。このお札を納める場所として、神棚が一般家庭に定着したとされています。
■神棚を家に祀るのはどういう意味があるの?
日本では、全てのものに神様が宿るとする「八百万(やおよろず)の神」の考えが古くから根付いています。家にも神様が宿るとされ、自分たちを守護してくださる神様を目に見える形でお祀りするため、家の中に神棚を設ける習慣が生まれました。
現代の神棚は、神様への感謝を伝え、家内安全や商売繁盛を祈願する場であるとともに、神様を大切にする心を通じて敬う心を育む場としても重要な役割を担っています。
【図説あり】神棚の設置に適した方角は?鬼門とは?

初めて神棚をご用意する際には、自宅内のどこに置くべきかを悩まれる方は少なくありません。
この項目では、家に神棚を設置する際の適した方角を解説します。また、避けるべき方角とされる「鬼門(きもん)」についてもご紹介します。
神棚の設置に適した方角

神棚を設置する際は、中にお祀りしているお札が、南向きまたは東向きになるように設置する形が一般的です。
日本人は農耕文化の中で太陽の動きを重視してきたことや、天照大神が太陽を司る神であることから、太陽が昇る東向きや、日差しが降り注ぐ南向きが重要視されてきました。
「鬼門(きもん)」の方角は避けるべきとする考えもある
風水において、北東の「鬼門(きもん)」や南西の「裏鬼門(うらきもん)」は不吉な方角であるという考えから、神棚の設置も同様に避けるべきとの考えもあります。
ただし、神棚の方角に絶対的な決まりはありませんので、南向きや東向き以外(西向きや北向き、鬼門など)の方角に置いていただいても問題はございません。
- 鬼門(きもん)…北東の方角。「鬼(邪気)の出入りする方角」を意味する
- 裏鬼門(うらきもん)…南西の方角。鬼門の反対側に位置する
神棚の設置場所|避けるべき場所はある?

神棚を置く際は、設置する方角だけでなく設置場所の検討も重要です。神棚は一度設置すると容易に移動させるものではないため、ご家族が安心してお参りできる環境を整えるためにも、安置場所を事前にしっかり検討することをおすすめします。
この項目では、神棚の設置に適した場所と、なるべく避けるべき場所をそれぞれ解説します。
神棚の設置に適した場所
神棚を設置する際には、適切な場所を選ぶことで、清潔さを保ち、ご家族がお参りしやすい環境を整えることができます。以下に、神棚を設置する際に押さえておきたいポイントを2点解説します。
1.人の目線より高く、天井に近い場所
神棚は、人の目線より高い位置にご安置するのが基本ですので、なるべく天井に近い位置に置くことで敬意を示すことができます。
神棚を取り付ける際は、天井から棚板を使って吊るす、台の上に置くなどの方法があります。詳しい設置方法については <こちら>の項目をご参照ください。
2.明るく清潔で、家族が集まってお参りしやすい場所
神棚は、ご家族がお参りしやすい場所に設置することも重要です。リビングや和室、ダイニングなど、清潔で明るく、自然と人が集まる場所が最適です。
なるべく神棚の設置を避けるべき場所
神棚を設置する際には、以下のような場所を避けるようにしましょう。以下に、神棚の設置を避けるべきポイントを4点解説します。
1.高さや位置に注意が必要な場所
神棚を目線より低い場所に置くと、神様を見下ろす形となり失礼にあたりますので避けましょう。また、神棚の上を人が通る場所も、間接的に神様を踏む形になってしまうため、同様に避けましょう。

もし上階に廊下や部屋がある位置にしか置けない場合には、神棚の上部に「雲」や「天」と書かれた文字を貼ることで、「神棚の上には何もない」ということを表現し、神様に敬意を払うことができます。
■神棚の雲について詳しくはこちら
神棚を設置した上に部屋がある場合に貼る「雲」について、その意味や貼る場面、種類、書き方、貼り方、処分方法を解説します。
2.家族がお参りしにくい場所
寝室や個室のようなプライベートな空間は、家族全員がお参りしにくいため避けるべきとされています。
また、玄関やドア付近など人通りが多く落ち着かない環境もお参りがしにくく、神様にとっても落ち着かない環境になるため避けましょう。
3.清潔さを保てない場所
神棚は清潔な環境に設置する必要があるため、水回りやトイレ付近などの汚れやすい場所、油汚れや熱気が発生するキッチンなどは避けましょう。
ただし、火の神様である「荒神様(こうじんさま)」をお祀りする場合は、例外的にキッチンが適しているケースもあります。
キッチンは基本的には避けるべき場所ですが、冷蔵庫の上であれば神棚を設置しても問題ないとされています。
一説には、食べ物は命を繋ぐために欠かせないものであり、その保管場所である冷蔵庫は神棚との相性が良いと考えられています。
4.お仏壇との配置関係に注意が必要な場所
神棚とお仏壇を同じ部屋に置く場合は、お参りの際にどちらかにお尻を向ける形となり失礼にあたるため、向かい合わせの配置は避けましょう。
また、神棚とお仏壇を上下に配置する形も、神様と仏様に優劣をつける形になってしまうため、神棚の下側にお仏壇を配置するような状態も避けましょう。
ただし、部屋のスペースに限りがあり、どうしても上下に近い位置に配置しなければならない場合は、以下のポイントを踏まえて置いていただくとよいでしょう。
- 神棚とお仏壇が真上と真下の位置関係にならないようにする
- 神棚とお仏壇の中心を左右にずらす
- 神棚を必ずお仏壇よりも高い場所に安置する
■神棚とお仏壇の置き場所について詳しくはこちら
神棚とお仏壇の両方を家に安置する方に向けて、部屋の中での適切な向きや置くべき配置について解説します。
■神棚のタブーについて詳しくはこちら
神棚の設置場所とお参りに関するタブーを中心に、よくいただくご質問もQ&A形式でご紹介しています。
神棚の設置方法・神具の飾り方

神棚を設置する際は、壁に取り付けた棚板に安置する形が基本ですが、近年は生活様式のモダン(洋風)化により神棚のデザインが多様化し、それに合わせて設置方法も様々になりました。また、神棚のデザインやサイズによって、お供えや神具の置き方が変わることもあります。
この項目では、棚板や台を使用した神棚の設置方法と、お供え・神具の基本的な飾り方を画像付きで解説いたします。
棚板や台を使用した神棚の設置方法
神棚の設置方法は、大きく分けて「棚板の上に神棚を乗せて壁の上から吊るす方法」、「壁掛けタイプの神棚を壁に直接掛ける方法」、「台や棚の上に神棚を直接置く方法」の3つがあります。
床に直接置くなど粗末な置き方でない限り、神棚のお祀り方法に絶対的な決まりはありませんので、生活環境にマッチするデザインの神棚を、日々のお参りがしやすい場所に設置するとよいでしょう。
設置方法①棚板の上に神棚を乗せ、壁の上から吊るす

神棚を設置する際に最も一般的な飾り方は、「棚板」や「吊り板」と呼ばれるL字型の木製台を壁に取り付け、その棚の上に神棚を置く方法です。
一軒家のご家庭や、会社に設置する際など、スペースに余裕がある場所に設置する際によく選ばれます。
棚板は、神棚のサイズに合わせた既製品が販売されていますが、中にはDIYで自作する方もいらっしゃいます。
もし手作りする際は、台を神棚の大きさにあわせてカットするなど慣れない作業で難しい場合もありますので、大工さんや工務店などへ取り付けを依頼するとよいでしょう。
設置方法②壁掛けタイプの神棚を、壁に直接掛ける

モダンな棚板と札立てがセットになった壁掛けタイプの神棚は、背面にフックが付いている場合が多く、壁に直接取り付ける形で設置します。
壁に穴をあける必要がありますが、モダンなデザインが多く、省スペースで飾れるため、マンションやリビングなどの洋室にもよくマッチします。
設置方法③台や棚の上に、神棚(札立て)を直接置く

スペースが足りなかったり、賃貸物件で壁に穴をあけられないなどの場合には、タンスや台の上に神棚を直接置いていただいても問題ありません。
また、近年では、そのまま台の上に置いて簡易にお祀りできる「札立て」もございます。ご自宅の安置スペースに合わせて、お参りしやすい形式の神棚を選ぶと良いでしょう。
お供え・神具の飾り方

神棚には、「米・塩・水」の3つをメインに、お酒、榊、季節の産物などもお供えします。
また、棚板の上にはしめ縄を飾り、お宮の手前には神鏡(しんきょう)や真榊(まさかき)、火立を置きます。
神棚の基本的なお供え配置
神棚のお供え物は、前後2列で並べる場合と、横1列に並べる場合の2パターンがあります。
お供え物は重要度の高い順に並べるのが基本です。米を最も重要なものとして神棚の中心(=神様に最も近い場所)に置き、その後に酒、塩、水の順でお供えします。榊をお供えするタイミングに特に決まりはないため、最初か最後にお供えすると良いでしょう。
■神棚の飾り方(祀り方)について詳しくはこちら
神棚のお供えに必要なものや具体的な飾り方(配置)、交換タイミングや処分方法のほか、神棚の簡易的なお飾り方法についても触れています。
神棚の「魂入れ」とお参り作法について

仏教でお位牌に「魂入れ」を行うように、神道でも新たに神棚を用意する際には「神棚奉斎(かみだなほうさい)」という御祈祷を行います。ここでは、神棚奉斎の方法や日々のお参り作法など、購入前に知っておきたい基礎知識を解説します。
神棚では「神棚奉斎(ほうちんさい)」を行う必要がある
仏教でお位牌に「魂入れ」を行うように、神道でも、新たに神棚を用意する際には「神棚奉斎(かみだなほうさい)」や「神棚奉鎮祭(かみだなほうちんさい)」と呼ばれる御祈祷を行います。この儀式は、空間を清め(お祓い)、神様を神棚にお迎えし、家族を見守っていただくためのものです。
近年では、モダンな神棚をお祀りする家庭が増え、御祈祷を省略する場合もありますが、可能であれば実施することをおすすめします。
■御祈祷の依頼方法
御祈祷の方法は、神主様を自宅に招くか、神棚を神社に直接持ち込むかの2通りです。所要時間は20~30分程度で、費用相場は【5,000円~30,000円程度】が一般的です。
依頼時には、御祈祷の有無や費用のほか、もしご自宅で執り行う場合には、当日用意すべきお供え物についても、事前に神社へ確認しておくと安心です。費用をお支払いする際は、無地の封筒か、「初穂料」や「玉串料」と記載した封筒に包み、当日直接お渡しいただく形がマナーです。
神棚を用意(購入)するタイミング
神棚の購入時期に特に決まりはありません。「思い立ったが吉日」として、家内安全や商売繁盛、諸願成就を願ってお祀りしましょう。
新築やリフォーム、引越し、お店の開店、結婚、出産など、新しい生活の節目に用意するケースが一般的です。
■神棚の購入について詳しくはこちら
初めて神棚を購入する方に向けて、神棚の購入場所や値段の違いなど、神棚の購入に関する基礎知識を解説します。おすすめの神具付きセットもご紹介しています。
購入後の日々のお参り方法
神棚にお参りする際には、守るべき作法(マナー)があります。この作法は多くの神社でも共通しており、習慣化することでよりスムーズに行えるようになります。
事前に手や口をすすいで身を清め、お供え物を整えてからお参りしましょう。
お参りのタイミングと基本作法
お参りのタイミングや回数に明確な決まりはありませんが、朝や夕に挨拶を兼ねてお参りするのが一般的です。「身口意(しんくい)」という考え方に基づき、行動・言葉・気持ちを大切にすることが重要です。
また、お参りの際には「二拝二拍手一拝(にはいにはくしゅいっぱい)」の作法を基本として行いましょう。
二拝二拍手一拝の手順

① 二拝…姿勢を正し、腰を90度ほど曲げて2回深く礼をします。

② 二拍手…胸の前で手を合わせ、右手を少し下にずらして2回手を打ち、そのまま両手を合わせて祈ります。

③ 一拝…最後にもう一度90度ほど腰を曲げて礼をします。
より丁寧にお参りしたい際には、「祝詞(のりと)」を奏上する
より丁寧なお参りの際は、「神棚拝詞(かみだなはいし)」と呼ばれる祝詞(のりと)を読み、その後に二拝二拍手一拝を行います。祝詞とは、神様への感謝や祈りを言葉にしたものです。
■神棚拝詞
此(こ) の神床 (かむどこ)に坐(ま)す掛(か)けまくも畏(かしこ)き天照大御神(あまてらすおおみかみ)・産土大神等(うぶすなのおおかみたち)の大前(おおまえ)を拝(おろが)み奉りて恐(かしこ)み恐(かしこ)みも白(もう)さく大神等(おおかみたち)の広き厚き御恵を辱(かたじけな)み奉り高き尊き神教(みおしえ)の随(まにま)に直(なお)き正しき真心もちて誠の道に違うことなく負い持つ業(わざ)に励ましめ給(たま)い家門(いえかど)高く身健(みすこ)やかに世のため人のために尽 くさしめ給えと恐(かしこ)み恐(かしこ)みも白(もう)す
■祝詞の意味
この神棚に仰ぎまつる、言葉にだすことも恐れ多い天照大御神、この土地にお鎮まりになっている産土大神の御前を拝して謹んで申し上げます。
神々の広く厚い御恵みをもったいなく思い、高く尊い神の教えのとおり、素直で正しい真心によって人の道を踏み外すことなく、従事する勤めに励むことができます様に、また家が栄え、家族も健康で世のため、人のために尽くさせてくださいと、恐れ多くも(謹んで)申し上げます。
神棚関連記事はこちら
「神棚・神具」の通販サイトはこちらです。
おしゃれでシンプルな神棚や札立て、神棚人気ランキングなどを掲載し、動画でも紹介しています。神棚を設置する方角、神具の飾り方などの基礎知識も解説しています。
この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。