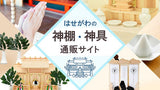購入場所はどこ?4つの販売している場所を説明

神棚は頻繁に購入するものではありませんので、いざ用意をしようと思うと「どこで買えるんだろう?」と思うかもしれません。ここでは、神棚が手に入る場所を紹介します。
そもそも神棚ってなに?
神様をお祀りする場所です。日々生かされていることへの感謝をお伝えし、家内安全や商売繁盛を祈願するための場としての意味を持ちます。また、神様を敬う心を通じて心の豊かさや美しさを養い、次世代へと継承していくことにも繋がるとされています。
神社で用意する

伊勢神宮や出雲大社など、神職様が常時いらっしゃるような規模の神社では、神棚を販売している場合もございます。ただし、販売スペースの関係から、取り扱っている神棚の種類やデザインが限られることもあります。
多くの神社ではお札やお守り、御朱印の授与が中心となるため、神棚の取り扱いが不明な場合は事前に確認しておくと良いでしょう。
神社で神棚を購入する際のメリットは、神職様から直接アドバイスを受けられる点です。また、疑問や不安をその場で相談できるため、初めて神棚を購入する方にも安心です。
また、神棚に納めるお札も同時に授与いただくことができ、スムーズな購入が可能です。
神棚は購入後にお祓い(お仏壇で言う「魂入れ」)が必要ですが、神社で購入した場合は既にお祓い済であることも多いため、購入時に確認しておくと良いでしょう。
専門店(神具店・仏壇仏具店)で用意する

・神道(神棚)に関するものを取り扱う神具店(神棚メーカー)もあります。街中で見かけることが少ない地域もあるかもしれませんが、大きな神社などの近くでは見かけることがあります。
・仏壇仏具店でも神棚を購入できます。神棚・神具コーナーがあり、榊立や雲、台など販売されています。単体のロードサイト店だけでなく、ショッピングセンターや百貨店にお店をかまえていることも多く、買い物しやすい形態になっています。
はせがわ でも神棚・神具の取扱いがあります。どのような商品があるか・神棚のイメージをつけるためにも、まずは下見がおすすめです。お近くの店舗を探す>>
サイズやデザインのバリエーション豊富な点がメリットでしょう。また神具も取扱いがあるため、一緒にバランスをみながら選ぶことができます。
専門スタッフと相談をしながら検討ができ、アドバイスももらうことができます。
ホームセンターで用意する

最近では神棚・神具を置いているホームセンターも多くなりました。
神棚の設置に必要な工具なども購入することができます。
専門店ではないため、敷居が低く感じ気軽にお店に立ち寄ることができるでしょう。
店舗の大きさによっても神棚コーナーの充実さはかわりますが、比較的安価で求めやすい価格帯のものを扱っていることがメリットになるでしょう。
専門のスタッフではないため、困ったことなど具体的な相談はできないことは注意しましょう。
ECサイト(通販)で用意する

近くに専門店やホームセンターがない場合でも簡単に購入ができます。専門店の通販サイトもあれば、そうでないサイトなど多数あります。
多くの商品を見ることができますが、目の前に店員がいないためスムーズな質問はできません。問い合わせ先の電話やメールなどを活用し、疑問を解決しましょう。はせがわ のオンラインショップ>>
営業時間を気にすることなく、インターネット環境があれば好きな場所・タイミングで商品の検討ができます。
実物を見ることができないため、記載されている寸法などをよく確認しましょう。専門店のECサイトであればネットで検討をしてから、実店舗で商品を見ることも可能でしょう。
神棚の値段は?主な要因を紹介

神棚は主に使用している材質により価格が変わります。比較的に値段のしっかりしたものほど装飾や細部の作りが繊細で豪華になる傾向もあります。
<材質>だけでなく、お部屋にあわせ<デザイン>も検討要素にされるとよろしいでしょう。
お札だけを祀るのであれば3,000円程度から、神具もしっかり飾るのであれば20,000円程度から20万以上と幅広くあります。安いものから高級なものまであり、デザインなど含め総合的に検討をするとよろしいでしょう。
神棚を探す>>
主に材質(木材)によって変わる
よく使われる木材は、桧や欅などがあります。近年はモダンで洋風な神棚も増えているため、家具でも使用されるウォールナットなどの材質もみられるようになりました。
桧(ひのき)
木目(柾目)が美しく、水気・日照りに強く、狂いが少ないことが特徴です。神具や祭具、神殿をはじめ金仏壇を造るのに良い木材です。
桧の中でも特に、木曽桧が伊勢神宮にも使われ有名であり、同じ材質が最上級とされています。現在は国有林として年間の伐採量が管理されているため、希少なものになります。
欅(けやき)
日本人に親しみ愛されてきたニレ科の和木です。重厚で耐久性に富み、建築材としても多用されています。狂いの少ない木材として神社仏閣に用いられ、神棚に使われる場合は高級品として取り扱われています。
その他の材質
シンプル、札立などのモダンなものではウォールナットやメープルを使用した神棚もあります。家具でも多く使用されている材質です。また陶器やガラスなど木材以外のものと組み合わせたデザインもありバリエーションが豊富になってきています。
デザインによって変わる
デザインがシンプルなもの、本格的なもの、モダンなものなど多くの種類が神棚にはあります。ここでは主だったデザインを紹介します。
神明造り(しんめいづくり)

伊勢神宮の社殿の形を模した「神明造り(しんめいづくり)」が一般的な形です。
その中でも、扉が1つの一社宮と、扉が3つの三社宮があります。屋根には茅葺(かやぶき)が用いられることもあります。
箱宮(はこみや)

箱宮は、お社を箱型のケースに収めた神棚の一種です。もともとは、北海道や東北などの寒冷地で、囲炉裏のススや汚れからお社を守るために生まれたデザインです。
棚板を使わず壁に掛けられるタイプもあり、掃除がしやすく神具をすっきり納められるため、現在では地域を問わず広く活用されています。
札立て(ふだたて)

札立ては、お札を簡単にお祀りできるコンパクトな神具です。場所を取らず、自由でモダンなデザインが多く展開されているため、洋室やリビングなどにも調和しやすく、近年人気が高まっています。
どのようなデザイン・サイズの神棚を選んでも問題はありません。
購入前に神棚の内寸を確認するようにしましょう。
当社人気ランキング
(神棚)※独自集計
用意に困ったら神具付き神棚セットがおすすめ!

お供えに使用する榊立などの神具は単品で販売されています。割れたなど追加で単品購入したい場合は便利です。
はじめて神棚の用意をする場合は「道具(神具)は何を買えばいいのか」「神具のサイズがわからない」など悩むことがあります。専門店ではスタッフがおすすめのサイズを紹介してくれます。
神具が一式揃った神棚セット

これから神棚を一式用意する場合は、必要なお道具一式と神棚がセットになった、神具付き神棚セットもおすすめです。
商品が届き次第、すぐにお祀りすることができます。
神棚・神具は、購入するタイミングに決まりはありません。お札をもらった時・新築引越し・出産・入学・入社など節目で検討される事もあります。
神道には「浄明正直(じょうみょうしょうじき)」といって、清く・明るく・麗しい心を大切にする考えがあります。新しいうちは神様の力が強く、古くなると神様の力が弱まるとも考えられます。神棚もどんなに長くても、20年を目安に取り替えるとよろしいでしょう。
神棚を購入したら?「神棚奉斎(かみだなほうさい)」をしよう

神棚を用意した後には、「神棚奉斎(ほうさい)」または「神棚奉鎮祭(ほうちんさい)」をされると丁寧です。
空間を清め(お祓い)、神様が神棚にお鎮まりいただき家族を見守ってくださいとご祈祷するものです。モダンで簡略化した神棚も多く、実施していない家庭もありますが可能であれば実施したいものです。
神主様を自宅に招く・神社へいく、2つの方法があります。時間は20~30分程度、費用は5,000円から30,000円程度になります。事前に神社へ「神棚奉斎」の実施の有無や費用など確認をするとよろしいでしょう。自宅でおこなう場合には用意するべきお供えも確認しておく必要があります。料金は無地の封筒または、表に「初穂料」「玉串料」と記載するとよろしいでしょう。
神棚は、経年劣化や引越しなどのタイミングに応じて、新しいものにお買い替えいただいても問題ありません。
買い替えた際は、古い神棚を神社で祈祷し、お焚き上げ(処分)する形が一般的です。
■神棚の処分について詳しくはこちら
神棚の処分方法4選・費用相場
神棚の処分・交換タイミングと方法、費用相場などを具体的に解説します。神具やお供え(お米や塩)の処分方法についても触れています。
神棚関連記事はこちら
「神棚・神具」の通販サイトはこちらです。
おしゃれでシンプルな神棚や札立て、神棚人気ランキングなどを掲載し、動画でも紹介しています。神棚を設置する方角、神具の飾り方などの基礎知識も解説しています。
この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。