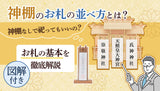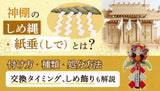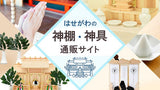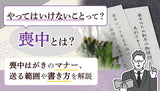お彼岸の食べ物っていつもと違うの?

「せっかく親族が集まるんだからとにかくみんなが好きなものをお腹一杯食べる」という選択肢もあるかと思いますが、ここではお彼岸の意味をお伝えすることで、なぜ普段と少し違うものを食べるのかをお伝えします。
お彼岸の食事は修行の1つ
お彼岸の語源は、サンスクリット語の「paramita(パーラミタ)」です。「彼岸に至る」という意味です。
仏教伝来より、日本では現世を「此岸(しがん)=こちらの岸、欲や煩悩にまみれた世界」、悟りの世界を「彼岸(ひがん)=向こう岸、仏の住むお浄土の世界」と考えます。教えに従って精進する(修行を行う)ことで、煩悩や生老病死に満ちた世界を脱して悟りの境地に至ることができるとされました。
お寺で僧侶がよく食べる物を食することも、実は精進(修行)の1つなのです。
3月の春分の日と9月の秋分の日は、「あの世(彼岸)」と「この世(此岸)」が最も近付く日とされるため、仏教において重要な意味を持ちます。
なぜお彼岸は3月と9月にあるの?
仏教では、西方の遥か彼方にお浄土の世界があるとする「西方浄土(さいほうじょうど)」の考えがあります。
お彼岸は太陽が真東から出て真西に沈む期間であり、西方にあるお浄土への道しるべができると考えられていました。昼夜がほぼ同じ長さになる期間であり、1年の中でお浄土との距離が最も近くなるため想いが通じやすくなる時ともされています。
■お彼岸について詳しくはこちら
お彼岸とは、春(3月)と秋(9月)の年2回に行われる仏教行事です。このページでは、お彼岸の意味や具体的なお彼岸日程、4つのやるべきことなど、お彼岸の基本を解説しています。
お彼岸におすすめの食べ物は?タブーはある?

お彼岸の時期には、家庭での食事をはじめ、お仏壇やお墓参り時の来客に対するおもてなしなどでも、お彼岸ならではの食べ物を用意することが一般的です。
この項目では、お彼岸におすすめの料理をご紹介します。また、お彼岸時期にはなるべく避けるべき食べ物についても、 <こちら>の項目で解説しています。
精進料理

精進料理とは、仏教における不殺生の教えに基づき、肉や魚などの動物性食材を使わずに作られた料理のことを指します。
お彼岸においても、ご先祖様への供養として、お仏壇に「御霊供膳(おりょうぐぜん)」と呼ばれるお膳を用いて精進料理をお供えします。
お湯をかけるだけで簡単に作れる、便利なフリーズドライ製の精進料理セットもございます。詳しくは <こちら>の項目をご参照ください。
■御霊供膳の並べ方について詳しくはこちら
御霊供膳の宗派別の並べ方や使うタイミング、メニュー例など、御霊供膳に関する基礎知識を解説します。
そば・うどん

「彼岸そば」「彼岸うどん」といった呼ばれ方でおそばやうどんを食べる地域があります。
「年越しそば」や「運ドン」など「そば」や「うどん」は縁起が良いとされたり、弱った胃腸を整え、内臓をきれいにする食べ物とも言われています。
お赤飯

小豆の赤い色が魔除けの色であることから、節分の豆まきの豆は小豆が使われていました。小豆を使ったお赤飯も魔よけの食べ物として未だにお彼岸で食されることが多いです。
還暦祝いや七五三などといった慶事で赤飯を食べるのも同様の理由です。
天ぷら

魚や肉、卵の天ぷらを避け、野菜やキノコをあげたものを「精進揚げ」と言います。春彼岸にはタラの芽やたけのこ、秋彼岸にはきのこやナスなど季節に合った食材を使うことがおすすめです。
関西では「つけ揚げ」「衣揚げ」とも言います。忌中となる 四十九日までにもよく食されます。
いなり寿司・五目寿司

いなり寿司や五目寿司もお彼岸の代表的な食べ物の1つです。肉や魚を使わず、山菜やレンコンの酢漬けなどを使用して作ります。
酢飯に細かく刻んだショウガ、梅などを混ぜると日持ちが増すようです。
煮物(煮しめ)

お彼岸期間中に毎回違う精進料理を作るのは大変なため、日持ちする野菜を使って煮物を作っておくと便利です。
定番の煮物としては、鶏肉の代わりに車麩や豆腐を使った煮物のほか、春彼岸ならタケノコ、秋彼岸なら里芋など季節の素材を使った煮物が定番です。
煮物を作る際は、殺生を避けるため、かつお節や煮干しなどは使わず、昆布や干ししいたけなど植物性の食材で取っただしを使うと良いとされています。
汁物

精進料理や和食では、「一汁三菜」や「一汁一菜」と言うように汁物を重要視します。
こちらも肉や魚を使わないけんちん汁・きのこ汁、だいこんの味噌汁などが代表的です。
【おすすめ】故人様の好きだったもの

家族や親族と故人様の好きだったものを召し上がることで、自然と思い出話などで会話も盛り上がります。作る過程でも故人様の事を思い出すいい機会にもなります。
故人様のことを想うことは立派なご供養となるため、おすすめです。
上記の食べ物の他にも、季節の食べ物(かぼちゃなど)を使用した料理を食べる場合もあります。絶対的な決まりはありませんので、地域やご家庭のお考えに応じてご用意いただくと良いでしょう。
お彼岸の中日に食べるべきものはある?
お彼岸の中日は、それぞれ春彼岸は「春分の日」、秋彼岸は「秋分の日」と定められています。地域によっては、「入りぼたもち(おはぎ)に明け団子、中(なか)の中日(ちゅうにち)小豆飯(あずきめし)」という言葉が伝わっており、お彼岸の入り(初日)と明け(最終日)にはお彼岸団子をお供えし、中日にはお赤飯を用意する風習が見られます。
お彼岸に食べてはいけないものはある?
地域やお寺によっても異なりますが、仏教では一般的に殺生を禁じているため、「三厭(さんえん)」と呼ばれる獣・魚・鳥などの食べ物は食べない方が良いという考えがあります。
また、香りが強い食べ物もNGとされているため、「五葷(ごくん)」と呼ばれる、ニンニク・タマネギ・ネギ・ニラ・ラッキョウなども避けるべきとされています。もし不安な場合は、お世話になっているお寺などにご相談していただくと安心です。
お彼岸時期のお仏壇には、どんな食べ物をいつお供えする?

ご先祖様への感謝の気持ちを込めて供養を行うお彼岸には、お墓参りや法要を執り行うほか、自宅のお仏壇へのお供えも一般的です。また、他家に訪問してお参りする際には、手土産を持参する風習もあります。
お彼岸のお供えとしては、お花やお線香なども定番ですが、この項目では食べ物のお供えに焦点を当て、何をいつお供えすると良いのかをご紹介いたします。また、手土産の費用相場についても触れています。
お彼岸のお供えにおすすめの商品については、 <こちら>の項目でご紹介しています。
おはぎ・ぼたもち

お彼岸のお供えとして最も定番なのは、もち米と餡子を使用した和菓子である「おはぎ」と「ぼたもち」です。
季節によって呼び方に違いがあり、3月の春彼岸には春に咲く牡丹の花にちなんで「ぼたもち(牡丹餅)」、9月の秋彼岸には秋に咲く萩の花にちなんで「おはぎ(御萩)」と呼ばれています。
■おはぎとぼたもちは、具体的に何が違うの?
諸説ありますが、「ぼたもち」は、大輪を咲かせる牡丹の花に見立てて、丸く大きめに「こしあん」で作ります。もう一方の「おはぎ」は、萩の花に見立てて小振りな俵型にし、小さな花びら1枚1枚を模して「粒あん」で作ります。
ただし近年では、スーパーなどで年間を通して 「おはぎ」 の名称で販売されることが一般的になっています。
お彼岸におはぎやぼたもちを食べるのはなぜ?
お彼岸におはぎやぼたもちといった小豆を使ったお菓子を食べるのには理由があります。一説には、小豆の赤い色は魔除けの効果があり邪気を払うとされていることや、昔は貴重品だった砂糖を使用した食べ物をお供えすることで、ご先祖様への敬意や感謝の気持ちを伝えるためとされています。
また、自宅までお参りに来てくださった親族や知人へのおもてなしとして、ご親族へ疲れを取っていただくためのお茶菓子にもおすすめです。
■お彼岸に食べるおはぎ・ぼたもちについて詳しくはこちら
食べる季節やあんこの違いなどの観点から、おはぎとぼたもちの違いを解説します。お彼岸時期に食べる理由やいつ食べるか、作り方などもご紹介します。
お彼岸団子

地域によっては、お彼岸をはじめ、仏事の際にはお団子をお供えする風習があります。
お彼岸においては「お彼岸団子」と呼ばれ、白く丸めたお団子を積み重ねてお供えします。
一般的には、お彼岸の初日(彼岸入り)に供える団子を「入り団子」、最終日(彼岸明け)に供える団子を「明け団子」と呼びます。
地域によって形や積み方に違いが見られるのが特徴とされ、お団子を積み重ねる数にも絶対的な決まりはありませんが、基本的には6個お供えする形が多いとされています。
これは、死後の行き先は「地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上」の6つがあり、亡くなるたびに生まれ変わりを繰り返すという「六道(ろくどう・りくどう)」の考えに由来すると言われています。
果物

お仏壇を華やかに彩る果物は、お仏壇へのお供えだけでなく、他家に持参するお供え(手土産)としても適しています。
特に、長時間のお供えでも傷みにくい、日持ちする旬の果物(リンゴ・オレンジ・メロンなど)がおすすめです。
お仏壇にお供えする際は、「高杯(たかつき)」や「盛器(もりき)」といった、仏様への敬意を示す足つきの器を使用するのが一般的です。
お供え用の器の商品ページはこちら>>
菓子折り

日持ちしやすく小分けにできる菓子折りは、贈り先の家族構成を問わず渡しやすいため、他家へのお供えとしても人気があります。
お彼岸のお供えとしては、まんじゅうやおせんべい、羊羹(ようかん)などの和菓子が定番です。また、お子様や若い世代がいる家庭向けには、クッキーやマドレーヌなどの焼き菓子も人気があります。
もしどの菓子折りを買うか悩んだ際には、お彼岸の時期にデパートなどで販売される、手土産用のお菓子の詰め合わせセットを活用するのもおすすめです。
はせがわでは、日本人の生活にある「祈り」を「食」からひもとく事業として、「田ノ実 Tanomi」を展開しています。お供え物にちょうどいい、お手頃価格の菓子折りなどもお取り扱いしております。商品は、実店舗またはオンラインショップにてお求めいただけます。
故人様の好きだったもの
故人様が好きだったものは手土産にも向いています。ただし、もらった親族の方が困らないよう出来るだけ日持ちがするものや、好き嫌いの少ない食べ物のほうがいいでしょう。
手土産の費用相場はいくら?
お彼岸のお供えの費用相場は、【3,000円~5,000円程度】が一般的です。もし現金(香典)と品物を一緒に持参する場合には、総額が5,000円程度になるよう調整いただくと良いでしょう。
(例:現金3,000円+品物2,000円=総額5,000円)
また、故人と生前に親しかった場合や特別お世話になった方に対しては、【5,000円~1万円程度】と通常より高めにご用意する場合が一般的です。
ただし、あまり高額すぎると相手に気を遣わせてしまう可能性もあるため気を付けましょう。
お彼岸のお供えタイミングはいつからいつまで?
「お仏壇にお供えしているお膳はいつまでお供えすればいいの?」「親戚の家に手土産を持っていく場合、いつ行けばいいの?」など、お彼岸のお供えタイミングに関して不安のある方も多いのではないでしょうか。
以下に、一般的なお彼岸のお供えタイミングをご紹介します。
■お仏壇にお供えする場合
- 彼岸入り(初日)にお供えし、彼岸明け(最終日)に下げる形が基本
- お彼岸期間中は、常にお供えがある状態が望ましい
- 日持ちしない食べ物をお供えする場合は、中日(春分の日・秋分の日)を中心としたお供えがおすすめ
■実家や他家にお供え物を持参する場合
- お彼岸の期間中であれば、基本的にはいつ持参してもOK
- お彼岸中の訪問が難しい場合には、前もって渡すのがマナー(後ろ倒しにしない)
■お彼岸のお供えについて詳しくはこちら
定番のお供え物の紹介をはじめ、他家・実家へのお供え(手土産)の金額相場や郵送方法など、お彼岸のお供えについて基本を解説します。掛け紙(のし)の表書きマナーやお返しについても触れています。
お彼岸の食べ物で困った際のおすすめ商品

「お彼岸の準備をしっかりしたいけれど時間がない」「何を準備すればよいか迷ってしまう」といった悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
最後に、ご親族にもご先祖様にも喜んでいただける、お彼岸のお供えにぴったりのおすすめ商品をピックアップしてご紹介します。
おすすめ① フリーズドライの精進料理セット
ご先祖様に心を込めたお供えをしたい場合には、フリーズドライの精進料理セットが便利です。
本来、精進料理を一から準備するには手間がかかりますが、本品では、水を加えて電子レンジで温めるだけで手軽にご用意いただけます。
動物性の食材を使用せず、昆布だしを基調とした伝統的な味付けになっており、汁物・漬物・煮物・和え物が揃っているため、ご飯と合わせるだけで簡単に本格的な精進料理をお供えできます。
御霊具膳・精進料理セット
おすすめ② 食べ物を模したキャンドル(ローソク)や、ちりめん製のお飾り
「食べ物をお供えしたい気持ちはあるけど、管理が大変…」という方には、故人様の好物を模したキャンドルや、ちりめん製のお飾りもおすすめです。
おはぎやお団子などの和菓子、お茶やお酒などの飲み物を再現した商品があり、見た目も華やかで長期間美しく飾ることができます。
ほのかに甘い香りがついた商品もあり、煙や香りを召し上がるとされる仏様へのお供えとしても最適です。
故人の好物ローソクシリーズ
故人の好物ローソクシリーズをもっと見る
ちりめん製のお供えをもっと見る
おすすめ③ お湯をかけるだけで作れる、お麩のお吸い物

お麩(おふ)の中に味噌や具材が入っており、お湯を注ぐだけで簡単に用意できるお吸い物もおすすめです。
お麩は仏教と関わりが深く、精進料理にも古くから用いられてきた食材です。手軽に準備でき、保存性にも優れているため、お供えとしてだけでなく、手土産や急な来客時にも活用しやすい一品です。
>>法事ギフトの商品ページはこちら
※はせがわが展開する法事ギフト「田ノ実 Online」に移動します。
お彼岸関連記事はこちら
お彼岸の総合ぺージはこちらです。
お彼岸とは、春(3月)と秋(9月)の年2回に行われる仏教行事です。このページでは、お彼岸の意味や具体的なお彼岸日程、4つのやるべきことなど、お彼岸の基本を解説しています。
この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。