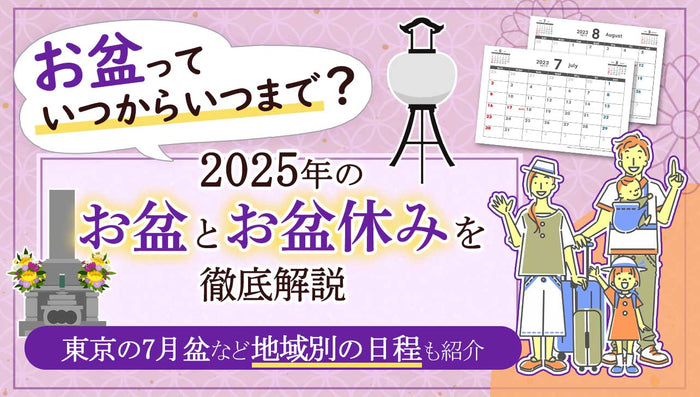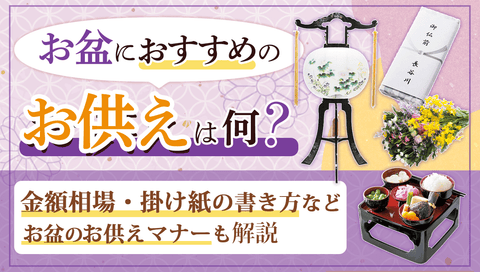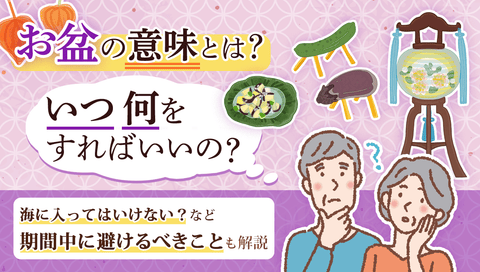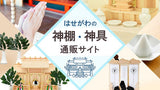2025年(令和7年)のお盆はいつ?お盆休みの日程は?

お盆の期間は、全国的には8月13日(水)~16日(土)の4日間ですが、地域によって7月や9月に行われる場合もあります。まず最初に、2025年のお盆期間はいつからいつまでなのか、地域ごとに詳しくご紹介します。また、一般的なお盆休みの日程についても触れています。
地域別のお盆期間
- 8月13日~16日(8月盆/旧盆/月遅れ盆)…一部地域を除く全国
- 7月13日~16日(7月盆/新盆)…東京都、神奈川県、石川県、静岡県の各一部地域(都市部)
- 7月31日〜8月2日…東京都多摩地区の一部地域
- 8月中旬~9月上旬…沖縄県
お盆の期間は、8月13日~16日の4日間(8月盆)が一般的ですが、東京をはじめとする一部地域では、7月13日~16日の4日間(7月盆)で行われます。また、東京の多摩地区では7月31日〜8月2日、沖縄県では8月中旬~9月上旬に行う場合もあります。
地域だけでなくお寺の考えによっても異なる場合がありますので、もしご不明の場合は、お世話になっているお寺や近所の方にご確認されるといいでしょう。
2025年(令和7年)のお盆期間は、【7月13日(日)~7月16日(水)】もしくは【8月13日(水)~16日(土)】です。
地域によってお盆の期間が異なる理由
- 旧暦...明治時代で新暦に変わるまで使用されていた暦
- 新暦...明治5年から現在にいたるまで使われている暦
お盆の期間が大きく7月と8月に分かれているのは、地域によって重視する暦(こよみ)が異なることが理由です。全国的には「旧暦」、東京などの都市部では「新暦」が重視される傾向にあります。
元々は月の満ち欠けを基準とした旧暦が使用されていましたが、明治時代に入って太陽の動きを基準とする新暦(グレゴリオ暦)が採用されたことにより、元々は7月だったお盆が新暦では8月となりました。
ただし、多くの地域は今までの慣習を簡単には変更できずに、そのまま旧暦の8月盆が継続されたことで、結果的に地域による違いが生まれたとされています。
一般的なお盆休み期間
仏事的なお盆が地域によって期間が異なる一方、お盆休みは全国共通で旧暦のお盆(8月盆)が基準になる場合が一般的です。
2025年(令和7年)の場合は、8月13日(水)~8月16日(土)が一般的なお盆休み期間となりますが、8月17日(日)は休日のため、【8月13日(水)~8月17日(日)】の5日間をお盆休み(夏季休暇)とする企業が多いでしょう。また、8月9日(土)、10日(日)の休日と、8月11日(月)の「山の日」(祝日)により、お盆直前が3連休となります。そのため、8月12日(火)に休暇を取得できる場合は、【8月9日(土)~8月17日(日)】の9連休が可能となります。
お盆が祝日ではないのに休みになる理由
お盆自体は祝日ではないにも関わらず、多くの企業がお盆を休日に指定しています。これは、江戸時代に存在していた、「藪入り(やぶいり)」と呼ばれる、夏時期に帰省する風習が受け継がれたことが理由とされています。
藪入りは、住み込み奉公をしている奉公人が、お正月とお盆の16日前後に休みをとって実家に帰ることができるという習慣で、現代においても年末年始・夏時期の帰省として残っています。特に、夏時期の帰省はお盆の風習と結びついたことで、家族や親族が揃ってご先祖様の供養を行う風習として根付きました。
※お盆の意味や由来についての詳細は、こちらの項目をご参照ください。
お盆休みの銀行や役所、交通機関はどうなる?
銀行は、「銀行法」の中で休日は土日祝と年末年始のみと定められているため、お盆期間中でも平日であれば通常通り営業しています。また、役所や郵便局も同様に土日祝以外は通常営業となります。しかし、病院については特段の決まりはなく、病院によってはお盆休みに合わせて休診にする場合もあるため注意が必要です。
電車やバスの交通機関についても、通常通りに平日は平日ダイヤ、土日祝は休日ダイヤで運行する場合が一般的なようですが、中にはお盆期間中は特別ダイヤを設定する場合も見られます。帰省やお出かけの際には、利用予定の交通機関ダイヤを事前に確認しておくと安心です。
お盆の期間中にやるべきこと5選

お盆は、あの世にいらっしゃるご先祖様や故人様をお迎えして感謝を伝える期間ですので、ご自宅で迎え火を焚いてお迎えし、お仏壇周りへのお盆飾りやお供え、お墓参りなどのご供養を行うのが一般的です。以下に具体的に解説いたします。
1.迎え火・送り火をしてご先祖様の送り迎えをする

お盆は、ご先祖様をご自宅にお迎えする行事ですので、お迎えの際には家の玄関先や庭先(地域によってはお墓)で「迎え火」を、お見送りの際には「送り火」をするのが通例です。送り火の際は、新盆用の提灯やまこも、牛馬なども一緒に燃やす場合もあります。
ただし、近年はマンションにお住まいの方も多く火が焚けない場合もありますので絶対ではありません。
■迎え火・送り火について詳しくはこちら
迎え火と送り火の意味をはじめ、実施日時や具体的なやり方、宗教や地域による違いなど、迎え火・送り火を詳しく解説します。
2.お仏壇周りへのお盆飾り・お参りをする

お盆には、故人様への気持ちを形で表すために、お仏壇の周りにお盆提灯や牛馬(なす・きゅうり)などのお盆飾りをしたり、果物やお花などのお供えを行います。
お盆初日にお飾りしても問題はありませんが、慌ただしくならないよう、お盆の1週間前など早めに準備しておくと安心です。
■お盆飾りについて詳しくはこちら
お盆飾りをいつどのように飾るのか、コーディネート例と共に画像付きで具体的に解説しています。
3.家族揃ってお墓参りをする

お盆時期には、家族揃ってお墓参りに行き、お墓掃除とお参りを行うのが一般的です。日にちに絶対的な決まりはありませんが、ご先祖様のお迎えの意味を込めて、13日(お盆入り)のお墓参りが最適とされています。
地域によっては、お墓で迎え火を焚いたり、お墓のローソクなどから「お迎え提灯」という手持ち提灯に火を移し、家まで持ち帰ってご先祖様を案内したりする風習が今も残っています。
お盆にお墓参りをする理由は何?
お盆のお墓参りは諸説あり、一説には、墓前で迎え火・送り火をするためにお墓へ行っていた習慣が残り、お盆時期にお参りするようになったとされています。
そのほか、中国から伝わった「魂魄思想(こんぱくしそう)」に基づき、家に帰ってきているのは故人様の「魂(=精神)」のみで、「魄(=肉体)」は変わらずお墓に眠っているとの考えから、魄にも手を合わせるためにお参りにいくとする説などもあります。
■お盆にお墓参りに行けない場合はどうする?
お休みが合わないなどの理由でお盆時期のお参りが難しい場合は、ご自宅のお仏壇やお位牌に手をあわせていただき、タイミングが合う時にお参りいただければ問題ございません。
お墓参りは本来いつ行ってもいいものですので、無理なく行ける時にお墓で手を合わせ、簡単でもお掃除をして差し上げることでご先祖様や仏様へ感謝の気持ちを伝えましょう。
■お盆のお墓参りについて詳しくはこちら
お盆のお墓参りにはいつ行くべきか、行ってはいけない日はあるのか解説します。掃除とお参りの仕方、持ち物、行けない時の対処法なども掲載しています。
4.お盆を迎えるご家庭にお供えを贈る

お盆を迎えるご家庭には、お線香などお仏壇まわりの消耗品やお菓子、果物のお供えをお贈りするのが通例です。宅配便で送るなら、先方が13日からのお盆に使えるよう日程に余裕をもって送りましょう。
■お盆のお供えについて詳しくはこちら
お盆におすすめのお供え物をご紹介します。贈答用の金額相場や、お供え物につける掛け紙の書き方などのマナーも解説しています。
新盆(初盆)のご家庭には、絵柄入りのお盆提灯をお供えしましょう
初めてお盆を迎えるご家庭には、ご親族や故人様と親しかった方から、お花や風景などの絵柄入り提灯を贈る風習があります。(地域によって異なる場合もございます)
なお、近年は、「お好きなサイズや絵柄の提灯を飾ってください」という意味を込めて提灯代(現金)を贈るケースもあります。
盆提灯
■新盆(初盆)の盆提灯について詳しくはこちら
新盆に飾る提灯の意味や飾り方、誰が購入するべきかなどを解説いたします。また、絵柄入り提灯の選び方や飾り方、処分方法などもあわせてご説明します。
5.家族・親族とこれからのご供養について話し合う

お盆には、普段なかなか集まるのが難しいご家族・ご親族が集まる機会ですので、これからのご供養について話し合うのもおすすめです。
お盆時期によくご相談のある話題としては、今あるお仏壇を見直してお仏壇のお買い替えを検討する、今あるお墓の処分(お墓じまい)や供養方法の変更を検討するなどが挙げられます。
お仏壇のお買い替えやお墓じまいの進め方にご不安がある場合には、お近くのはせがわまでお気軽にご相談ください。
かんたんWEB来店予約サービスはこちら>>
お盆にはどんな意味があるの?

ここまでお盆の期間と過ごし方についてご紹介して参りましたが、そもそもお盆とはどのようにして成り立ったのでしょうか?ここでは、お盆の意味と由来を簡単に解説いたします。
お盆の由来
お盆は、7月15日(または8月15日)に行なわれる夏の先祖供養行事のことを指します。
また「お盆」という言葉は、仏教における「盂蘭盆会(うらぼんえ)」、または「盂蘭盆(うらぼん)」を略した言葉とされています。その昔、お釈迦様のお弟子である目連様の母親が餓鬼道に落ちた時、お釈迦様の教えに従って多くの高僧たちに食べ物飲み物をふるまい、その施しの功徳が母を救ったところからはじめられたものとされています。
■お盆について詳しくはこちら
お盆の意味や由来、具体的にいつ何をするかなど、お盆に関する基本を徹底解説します。また、お盆時期に避けるべきことについても説明しています。
現代におけるお盆の意味
中国から入ってきた仏教にもとづく盂蘭盆会と、日本に古来よりあったご先祖様に感謝する習慣があわさったものが、お盆として現在まで伝えられてきました。最近は離れて暮らすことも当たり前となってしまったご家族が一堂に会す機会です。ぜひご先祖様や故人様への感謝と供養をしつつ、思い出話などに花を咲かせながら団らんする、大切な期間でもあります。
お盆帰省時におすすめの手土産

お盆の長期休暇で帰省する際には、手土産やお供え物を持って実家に帰省する方も多いのではないでしょうか?最後に、いざ選ぶとなると悩みがちなお盆帰省時の手土産について、定番品やおすすめ品をピックアップしてご紹介いたします。
お盆の手土産は、相手先に合わせて選びましょう
①渡す相手の環境に合わせて選ぶ
相手先の家にお仏壇がある場合には、お供え物も持っていくのが望ましいでしょう。
また、もし相手先にお仏壇がなく手土産のみを持参する場合も、子供がいる場合はアルコール類は控える、年配の方へ贈る場合は変わり種を避けるなど、贈り先の年齢層や人数に合わせて品物を検討しましょう。
②取り分けやすい個包装タイプのものを選ぶ
来客が多いご家庭の場合は、いただいた手土産を来客用に出す場合があったり、皆で分けて持ち帰ることができて便利なため、個包装タイプのものが喜ばれます。
③常温OKかつ日持ちするものを選ぶ
夏場は移動時間に傷んでしまう場合もありますので、常温OKの品物が望ましいです。また、すぐには食べきらなかったり、お供えの場合はお仏壇に長時間供えておいたりする場合も多いため、なるべく日持ちするものを選びましょう。
お盆の手土産におすすすめな品物をご紹介
帰省先への挨拶としての手土産なら【2,000円~5,000円程度】、お仏壇のお供え物なら【3,000円~5,000円程度】の相場を目安として品物を検討する形が一般的です。(贈り先との関係性にもって異なる場合もございます)
以下に、お盆の手土産としておすすめな品物をご紹介します。
①お菓子
手土産・お供え問わずメジャーなのは、個包装の日持ちする菓子折りです。
定番品はおせんべいやゼリー、どら焼きなどですが、他の方と被らないように、地域の名産品などを持っていくのもおすすめです。
②飲み物
飲み物も、手土産・お供えどちらにもおすすめの品物です。お酒が好きな家庭に贈る場合はお酒、子供がいる家庭ならジュースを選ぶのもいいでしょう。
お仏壇へのお供えなら、飲み物をかたどったローソク(故人の好物シリーズ)のギフトもおすすめです。
故人の好物ローソク
③お線香・ローソク
お線香やローソクはお参りで毎日使用しますので、お仏壇へのお供え物としては最も一般的です。特にお線香は「仏様はいい香りや煙を召し上がる」という「香食(こうじき)」の考えがあり、仏事的な面からもおすすめと言えます。
掛け紙は、新盆(もしくは初盆)のご家庭であれば「新盆(初盆)御見舞」、それ以外であれば「御仏前」「御供」と書くのが一般的です。
ギフト・贈答用仏具
④フラワーギフト
仏様はお花の香りも好んで召し上がると言われていますので、お花も定番のお供え物です。
近年は生花ではなく、日持ちする「プリザーブドフラワー」や造花のギフトを選ぶ方も増えています。
フラワーギフト
⑤季節の果物
季節の果物も、お供え物の定番の一つです。りんごやオレンジ、マスカットなどの果物の詰め合わせ(籠盛)が一般的です。
中には、夏場であることを踏まえてフルーツゼリーなどを選ぶ方もいらっしゃいます。
はせがわオンラインショップでは、のし(掛け紙)サービスのほか、専用のメッセージカード(お悔み挨拶状)もご用意しておりますので、お気軽にご用命ください。
お盆関連記事はこちら
お盆提灯の総合ぺージはこちらです。
お盆はご先祖様や故人様を優しくお迎えする風習です。2025年の新作盆提灯に加え、セット品や盆棚など豊富な商品紹介のほか、お盆の期間や意味、新盆についての解説もしています。
この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。