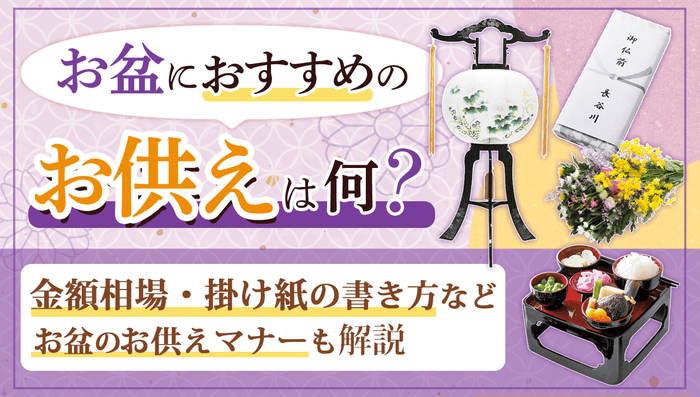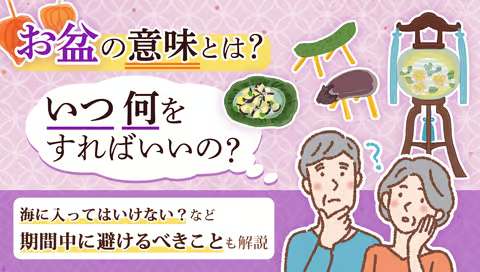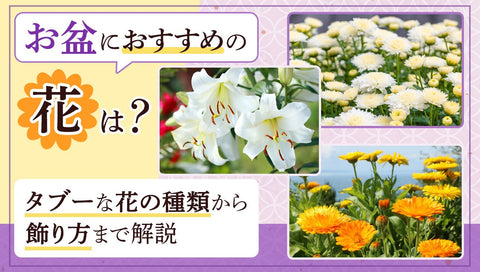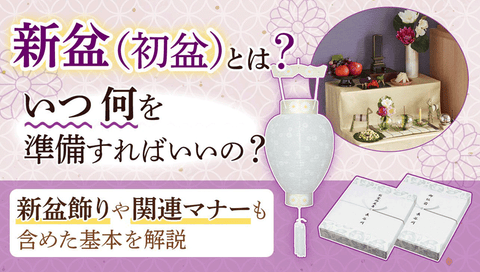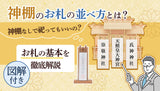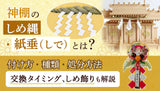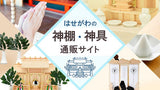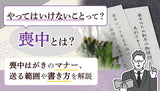お盆とは

お盆とは、ご先祖様の霊を自宅にお迎えしてご供養する夏の仏教行事です。お盆の期間は、8月13日~16日の4日間(8月盆)が一般的ですが、東京をはじめとする一部地域では、7月13日~16日の4日間(7月盆)で行われます。
お盆には、故人様やご先祖様への感謝の気持ちを込めて、盆提灯やお花などのお供え物をお飾りします。特に、故人様が亡くなってから初めて迎える「新盆(にいぼん)」は、故人様が初めて帰ってくる一度きりの機会のため、通常よりも盛大にお飾りして迎えるべきとされています。
■お盆について詳しくはこちら
お盆の意味や由来、具体的にいつ何をするかなど、お盆に関する基本を徹底解説します。また、お盆時期に避けるべきことについても説明しています。
お盆のお供えは「五供(ごく)」が基本

一般的に、仏事におけるお供えは「香」「花」「灯明(とうみょう)」「浄水(じょうすい)」「飲食(おんじき)」の5つが基本とされ、これら5つをまとめて「五供(ごく)」と呼びます。日々のお仏壇のお供えをはじめ、お盆時期のお供えもこの五供の考えに基づいて行います。
ここでは、五供それぞれの意味や由来を簡単に解説します。
1.香

香はお線香として日々のお参りでも使用されていますが、香りでその場所やお参りする人を清めるという意味と、香喰(こうじき)として仏様のご飯になるという意味があります。
また花・火・香の3つで「仏の三大供養」ともいわれ、とても大切なお供え物になります。
※「こうじき」は「香喰」「香食」とも書くことがあります。
2.花

花は仏様の慈愛と忍耐を表現し、さらには清浄も表すとされており、花・火・香の3つで「仏の三大供養」ともいわれ、とても大切なお供え物になります。
また、お参りする側に向けて飾ることで、私たちの心も清く落ち着かせてくれるとされています。故人様はお花の香りを好むとも考えられているので、葬儀でもきれいなお花で祭壇をお飾りします。
3.灯明(とうみょう)

ローソクなどの明かりのことです。仏様の智慧を表し、花・火・香の3つで「仏の三大供養」ともいわれ、とても大切なお供え物になります。
仏教では世の中を照らす役割があると考えられており、その明かりで迷いがなくなっていくとされています。
4.浄水(じょうすい)

水やお茶を供えることで、仏様の喉がかわかないようにという意味と、私たちの心を清らかにするという意味が込められています。
※宗派によっては、水やお茶を供えない場合もあります。
5.飲食(おんじき)

食べ物をお供えすることを飲食と言い、炊きたてのご飯やお菓子、季節の果物が多く用意されます。私たちと同じものを召し上がっていただくことで、仏様やご先祖様と繋がることができると言われています。
仏様は香りや湯気を召し上がるので、炊きたてのご飯などは固くなってしまう前に炊飯器に戻して皆さまで召し上がってください。お菓子なども、お供えが終わった後にはおさがりとして分け合っていただきます。
■お供え物に適していないものはあるの?
肉・魚などの殺生を連想されるもの、辛い物やにおいの強いものはタブーと考えられています。また、お花に関しては香りの強いものやトゲのあるものが避けられています。
お盆を迎えるご家庭へのお供え7選

新盆法要に参加したり、お盆を迎えるご家庭に訪問する際は、お供え物を持っていきます。お供え物は故人様に対する贈り物となりますので、基本的にはご家族へお渡しする手土産とは別にご用意すると良いでしょう。一般的には、お菓子やお花、お線香など「五供」に基づいた消費できるものがよく選ばれています。
以下に、お盆のお供えにおすすめの品物7選をご紹介いたします。
1.贈答用線香(進物線香)

法事をはじめ、日々のお参りでも使用できます。伽羅(きゃら)や沈香(じんこう)などの香木を使用した趣のある香りから、桜やラベンダーなどお花の香りまで様々です。
はせがわでは、無料で包装・掛け紙(のし)のサービスも承っています。
2.贈答用ローソク

法事をはじめ、日々のお参りでも使用できます。蜜蝋などの特別な材料のローソクは、燃焼した際に発生するススが少なくお仏壇が汚れにくいため、ギフトとして喜ばれます。お花などの絵柄が入った商品や、食べ物・飲み物を模して作られた「故人の好物ローソク」が贈答用に人気です。
3.絵柄入りの盆提灯

絵柄の入った提灯を、ご親族や故人様と親しかった方から贈ることがあります。昔ながらの伝統的なタイプもまだまだ人気ですが、最近は省スペースに飾られる方も増えてきており、小さくかわいらしいタイプの提灯も選ばれるようになってきました。
また、お好きなサイズや絵柄の提灯を飾ってくださいという意味で、「御提灯代」として現金を贈るケースもあります。
4.花(フラワーギフト)

季節の花を用いた花束やフラワーアレンジメントが贈答品として人気です。夏場は花が傷みやすいため、生花を特殊加工して長期保存可能にした「プリザーブドフラワー」もギフトに適しています。
初盆の場合は白色を基調とした組み合わせにするとよいでしょう。
5.ちりめんのお供え

小さなかわいらしい贈答品として、はせがわで人気のちりめんのお飾りがあります。毎年繰り返しお飾りでき、夏場などは傷まないお供え物としてお仏壇を華やかに見せてくれるため、ちょっとした手土産によく選ばれています。
季節限定デザインもあり、時期にあわせたお飾りをお楽しみいただけます。
6.お菓子

お参りにいらっしゃったお客様やご親族の方にも配れるので、焼き菓子など個包装されたものが人気です。また、すぐに消費できない可能性もあるので、常温で日持ちのするものを選びましょう。夏場ですのでゼリーもおすすめです。
百貨店をはじめ、スーパーマーケットなどで購入できます。
7.果物

季節の品物が選ばれます。なるべく消費期限が長く、常温で保存できるものにしましょう。百貨店をはじめ、スーパーマーケットなどでも購入ができます。
お供え用としてセットにして販売していることもあります。
8.飲み物

故人様の好きな飲み物が選ばれています。詰め合わせを用意されることが多いようです。百貨店をはじめ、スーパーマーケットなどでも購入ができます。
地域によっては、果物や飲料品を籠に飾り、花で飾った「盛籠(もりかご)」を贈る慣習もあります。
※盛籠は、はせがわの一部店舗(西日本地域)でもご注文が可能です。詳しくは店舗までお問い合わせください。
当社人気ランキング
(ギフト・贈答用仏具)※独自集計
■郵送の場合、お盆のお供え物はいつ送る?
お盆のお供え物を郵送する際は、お盆の入り(7月13日または8月13日)の1週間前~前日までには届くよう、余裕をもって送るといいでしょう。地域によってお盆の期間が異なりますので、ご不安な場合は事前に確認しておくと安心です。
お供えに付ける掛け紙(のし)の書き方・金額相場

お供えをお渡しする際は、包装紙で包んだ上から、「表書き」と渡す側の名前を記入した「掛け紙」をつけるのがマナーです。「表書き」とは、何の目的でいただいたか分かるように記入する、贈り物の目的に関する記載のことです。
※よく「熨斗(のし)」と混同されがちですが、のしはお祝いごと(慶事)用の名称であり、仏事やお悔みなどの弔事に使用するものは「掛け紙」と呼びます。
お供えの表書き・名前
お盆のお供えには、「御仏前」や「御供」の表書きを使用するのが一般的です。ただし、贈り先が新盆(初盆)の場合は、「新盆御見舞」(にいぼんおみまい)」を使用することもあります。
表書きの下には、どなたからいただいたか分かるように渡す側の姓名を記入します。もし連名にする場合には目上の方が右になるように記入しますが、人数が多い場合は「〇〇一同」としても問題ありません。また、ご夫婦の場合は夫の姓名を先に書き、その左側に妻の名前のみ記載する場合が一般的です。
御仏前
(ごぶつぜん)

四十九日(忌明け)法要以降に使用します。「御佛前」とも書きます。
御供
(おそなえ)

時を選ばずに使用できます。名古屋では御仏前よりも「御供」が多い傾向にあります。
新盆御見舞
(にいぼんおみまい)

新盆(初盆とも)で使用します。新盆とは四十九日法要が終わった後のはじめてのお盆をさします。
掛け紙の水引・文字色
水引は、白と黒のタイプのものを使用するのが一般的です。お盆は四十九日を終えたご家庭が行なうものなので、文字色は黒い墨で問題ございません。 (薄墨は四十九日前まで使用する色です)
百貨店や仏壇専門店などで購入する場合には、お供え用であることをお伝えするとサービスで掛け紙をつけていただけます。
お供え物の相場
お盆のお供え物の相場は【3,000円~5,000円程度】とされています。生前お世話になっていた場合などはもう少し高めでご用意する方もいらっしゃいますが、あまりに高額すぎると相手に気を使わせてしまいます。
ご自宅のお仏壇へのお供え8選

お仏壇には日頃からお供えをするものですが、お盆時期は故人様が自宅に帰ってくる1年に1度の機会ですので、いつもより盛大にお供えをします。他家へのお供え物と同様に、お菓子やお花、お線香など「五供」に基づいたお供え物が基本ですが、お盆特有のお盆提灯やそうめんなども定番です。
以下に、お盆を迎えるご家庭における、お仏壇への定番のお供え物をご紹介します。
1.盆提灯

帰ってくるご先祖様への目印として、昔は外に灯篭を高く掲げていました。今でもこの風習が残っている地域もありますが、これに足を付けて室内に置いたものが提灯です。昔は灯りが贅沢品でしたので、提灯飾りは最上のお供え物であり、多いほど良いとされました。
さらに提灯には「花」と「火」という、お仏壇でも大切にされている「三大供養」のうちの2つを表すという意味もあります。
■お盆提灯のご購入はこちら
お盆はご先祖様や故人様を優しくお迎えする風習です。2025年の新作盆提灯に加え、セット品や盆棚など豊富な商品紹介のほか、お盆の期間や意味、新盆についての解説もしています。
2.お線香

香りは仏様のごはんです。伽羅(きゃら)や沈香(じんこう)といった香木をはじめ、桜やラベンダーなどのお花の香りまでさまざまです。こちらも仏の三大供養のうちの1つである、「香」を表します。
3.ローソク

仏の三大供養のうちの1つである「灯明」です。ご家族がお仏壇や盆棚の前にいる時だけでも、ぜひ火を点けましょう。お盆には普段使いのローソクではなく、蜜蝋や絵柄の入ったローソクを使う方も多くいらっしゃいます。
また、食べ物や飲み物をかたどった「故人の好物ローソク」も人気です。本物だったらお供えのしにくいアイスをはじめ、ビールや枝豆など様々な形のローソクがあります。
4.お花

お花は仏の三大供養の「花」を表すだけではなく、お盆に帰ってくるご先祖様をにぎやかにもてなす意味もありますので、大きな花瓶にたっぷりとお花を入れましょう。
また、真夏のお盆はどうしてもお花が長持ちせず飾るのが難しいという方に向けて、近年はお盆用の造花ブーケも登場しています。普段は使わなくても、1~2つ持っているだけでお花が傷んできた時も安心です。
■お盆におすすめの花について詳しくはこちら
お盆の花の種類は菊や竜胆などが定番ですが、どのような意味があるのか、おすすめの花から避けられているタブーな花まで解説をします。
5.精進料理

殺生を避けるという考えから精進料理があります。5つの器に料理を盛りつけ、お箸は仏様側に向けます。お供えするお料理は一般的に以下の5つとされています。
- 親碗(ご飯)
- 汁椀(お吸い物・みそ汁)
- 腰高(香のもの・漬もの)
- ツボ椀(煮物・あえもの)
- 平椀(煮物)
精進料理をお供えする際は、「御霊供膳(おりょうぐぜん)」と呼ばれる、仏様やご先祖様に精進料理をお供えするための小型のお膳(器)に入れてお供えします。
5つの器と箸がセットになっており、お仏壇や葬儀後の後飾り祭壇、盆棚などに飾って使用します。
■時間がない方・料理が苦手な方にも大人気の「フリーズドライ精進料理」
精進料理素材セット「ご先祖さま」を使用すると、水を加えて電子レンジであたためるだけで手間なくお手軽に本格的な精進料理が作れます。汁物、煮物、和え物、漬け物が1食分セットになっており、レシピいらずです。
※ご飯は入っていません。
6.そうめん

夏の定番そうめんは、地域によっては茹でた状態でお供えをします。
「幸せがながく続くように」「故人様が荷物をくくる」などの意味が諸説あるとされています。
■お盆の定番料理について詳しくはこちら
お盆で定番のお供え物や精進料理、お盆ではタブーとされる食べ物について解説しています。
7.お菓子

お盆には「落雁(らくがん)」と呼ばれるお菓子がよくお供えされます。
その他にも、焼き菓子やゼリー、水羊羹など常温で日持ちするお菓子がよく選ばれます。
近年は、気温や賞味期限を気にせずお飾りできる、イミテーション(作り物)のお供え菓子も人気です。
イミテーションのお供え菓子の商品ページはこちら>>
■落雁(らくがん)って何?どうしてお供えするの?
落雁は、砂糖とでんぷんを含む穀粉(米や大豆など)で作られる砂糖菓子で、和菓子屋をはじめ、スーパーマーケット、百貨店、オンライン通販などで購入できます。
蓮や菊の花の形をしたものが多く、淡い色合いが特徴です。水分量の少ない「干菓子」の一種であるため、夏場でも日持ちします。
かつて釈迦如来の弟子である目連(もくれん)尊者が、自分の亡き母親や恵まれない人々に対して100種類を超える食べ物を施す「百味飲食(ひゃくみおんじき)」を行った際、当時貴重だった甘い物はお供え物として特に良いとされていたため、落雁を供えたといわれています。
その話がきっかけとなり、落雁をお盆にお供えすることが定番となりました。(諸説あります。)
8.果物

季節の品物が選ばれます。消費期限の長く、常温で保存できるものにしましょう。「盛器(もりき)」や大きなお皿などに乗せてお供えください。
いつからいつまでお供えする?
お盆のお供え物は、お盆飾りのお飾りタイミングに合わせて、お盆の入り(13日)に間に合うようにお供えし、お盆の終わり(16日)の故人様のお見送りが終わった後に下げるといいでしょう。
精進料理(お膳)は、【1日に3回(朝・昼・晩)】のお供えが望ましいとされています。私たちの食事の前にさしあげ、食事が終わったら一緒に下げるといいでしょう。ただし、もし毎回のお供えが難しい場合は回数を減らしても問題はありません。 ※地域やご家庭により、お供えをする日が決まっている場合もございますのでご注意ください。
お盆飾りの仕方は?お供え物はどこに置く?
お盆のお飾りは、お仏壇の前または横に盆棚を置き、盆棚の上や周囲を中心に飾ります。一般的には、盆棚の最上段にお位牌をお祀りし、それより下の段にお供え物仏具(お参りの道具)を置きます。
お盆の飾り方はお住まいや地域によって異なる場合もありますが、一例をご紹介いたします。

②霊前灯
③お位牌
④蓮型ローソク
⑤盆花
⑥盆花用 花瓶
⑦御霊具膳(おりょうぐぜん)
⑧花立
⑨火立(ローソク立て)
⑩蓮の葉
⑪水の子
⑫香炉
⑬みそはぎ
⑭盛器
⑯牛馬
⑰まこも
⑱経机・供物机
⑲盆棚・どんす
⑳導師布団
㉑花瓶
㉒リンセット
㉓行灯(盆提灯)
㉔新盆用白紋天
㉕ローソク型電池灯(吊り下げ提灯用)
㉖おがら
㉗ホーロク
※㉔~㉗は、基本的に家の軒先に飾る(置いて使用する)ものです。
■お盆飾りについて詳しくはこちら
お盆飾りをいつどのように飾るのか、コーディネート例と共に画像付きで具体的に解説しています。
新盆(初盆)のお供えは何か違いがある?
初めてお盆をお迎えする場合は「新盆(または初盆)」と言います。お供え物は新盆だからといって何か変わるわけではありませんが、故人様が初めて帰ってくる新盆は、特別賑やかにおもてなしをして差し上げると良いと言われています。故人様がお好きだったものをはじめ、お食事やお供え物をたくさんご用意してさしあげましょう。
お盆飾りは白紋天を飾る以外は基本的に通常のお盆と変わりませんが、初盆は法要やお参りのお客様が多い場合があります。
■新盆(初盆)について詳しくはこちら
新盆法要の準備方法や飾り付けの仕方、法要当日の服装やお見舞い挨拶などの基本マナーを解説します。
お供え物の片付け方

お盆の最終日である16日に「送り火」を行って故人様を無事お見送りしたら、当日中もしくは翌日以降にお盆飾りとお供え物を片付けます。以下に、お供え物の片付け方と処分方法をご紹介します。
食べ物のお供えの片付け方
お菓子や果物、精進料理(お膳)などの食べ物は、粗末にせずに家族でいただくのがマナーです。
一度お供えしたものを自分たちが食べるのは失礼なのではと不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、仏教の世界では、お供えをいただくことは「お下がり」といい、一度仏様にお渡ししたものをいただくことで、仏様への感謝や今生きていることのありがたみを感じることができる大切な行為だとされています。
また、お参りに来られたお客様やご親族に分けたり、お土産としてお渡したりする形で対応しても問題はありません。
ただし、もしどうしても食べきれなかった場合は、半紙やキッチンペーパーなどの白い紙に包んで、ごみとして処分しましょう。
食べ物以外のお供えの片付け方
絵柄入りのお盆提灯は来年以降も使用できますので、購入時に箱に入っていた状態に戻し、虫よけ(しょうのう)を添えて片付けます。
そのほか、お線香やローソクなど、日頃のお参りでも使用しているものはそのまま使っていただき問題ありません。お花についても、傷んでいなければそのままお飾りしていても大丈夫です。
よくある質問

お盆のお供えに関するよくある質問についてお答えします。
Q1. 宗派によってお供えするものに違いはありますか?
A. 浄土宗や真言宗など、浄土真宗を除く在来仏教では特に大きな違いはありません。
寺院によっては独特のお供えをする場合もありますので、気になる方は菩提寺の住職に相談されるとよいでしょう。
浄土真宗は教義の違いから、お盆独自のお供えやお盆飾りは必要ありません。ただし、地域によっては浄土真宗用の「切子灯籠(きりこどうろう)」を飾る場合があります。(九州地方など)
■浄土真宗のお盆について詳しくはこちら
浄土真宗のお盆の過ごし方を知りたい方に向けて、仏壇飾りやお供え、新盆(初盆)法要など基本を解説いたします。また、提灯のお飾りについても触れています。
Q2. お盆のお供え物にメッセージを添えて郵送しようと思います。どのようなことを書いたらいいでしょうか。
A. いくつか例文をご紹介します。内容や形式に決まりはありませんので、故人様との思い出やご遺族への配慮など、思いを綴られるとよいでしょう。
■お盆のお供え物に添える手紙の例文
- 新盆(初盆)を迎えられるにあたり、ご生前のご厚情に感謝すると共に改めて故人のご冥福をお祈り申し上げます。
- 新盆(初盆)を迎えられるにあたり、心ばかりではございますが、お線香(品物名)をお送りいたします。御仏前にお供えいただければと存じます。
- 新盆(初盆)を迎えられるにあたり、遠方より合掌させていただきます。暑さ厳しき折、くれぐれもご自愛ください。
特定の人物にあてた手紙(信書)を同封する場合は、必ず信書便で品物を送付しましょう。
※はせがわではお供え物に同封できる簡単な挨拶状(メッセージカード)をご用意しています。こちらは信書便ではなく、通常の宅急便で発送可能です。お気軽にご相談ください。
Q3. お盆にいただいたお供え物の返礼品に添えるお礼状を書こうと思いますが、どのようなことを書いたらいいでしょうか。
A. 香典やお供えものをいただいたことに対するお礼と、お盆(新盆・初盆)を無事に迎えられたことに対する感謝の意を記載します。
基本は縦書きで句読点は不要です。新盆法要に参列いただいた方には当日、お供えのみいただいた場合などは1か月以内を目途にお渡しします。
■お礼状(挨拶状)の例文
「拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます
この度 亡 〇〇 〇〇(故人様の氏名)儀 新盆(初盆)法要に際しましては ご多用中のところご鄭重なるご厚志を賜りまして心より厚く御礼申し上げます
おかげさまで 新盆法要を滞りなく済ませることができました
つきましては 供養のしるしとして 心ばかりの品をご用意いたしました 何卒ご受納賜りたくお願い申し上げます
ご厚情に感謝申し上げますとともに 今後も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます
本来であれば拝眉の上 御礼申し上げるべきところではございますが 略儀ながら書中をもちまして謹んでご挨拶申し上げます
敬具
令和〇年〇月〇日
郵便番号
住所
施主のフルネーム
親族一同」
お盆関連記事はこちら
お盆提灯の総合ぺージはこちらです。
お盆はご先祖様や故人様を優しくお迎えする風習です。2025年の新作盆提灯に加え、セット品や盆棚など豊富な商品紹介のほか、お盆の期間や意味、新盆についての解説もしています。
この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。